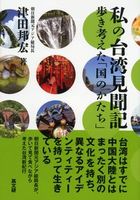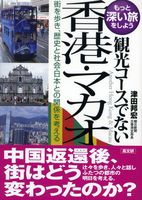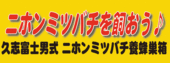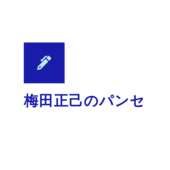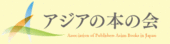- NEWS
アジア新風土記(109)タイの「司法クーデター」

|
著者紹介 津田 邦宏(つだ・くにひろ) 1946年東京生まれ。早稲田大学法学部卒業。72年、朝日新聞社入社。香港支局長、アジア総局長(バンコク)を務める。著書に『観光コースでない香港・マカオ』『私の台湾見聞記』『沖縄処分―台湾引揚者の悲哀』(以上、高文研)『香港返還』(杉山書店)などがある。 |
タイの憲法裁判所は2025年8月29日、ぺートンタン首相(39)にカンボジアのフン・セン上院議長との国境紛争に関する電話会談でのタイ軍幹部批判が憲法の定める閣僚の倫理基準に違反したとして解任の判決を言い渡した。
首相はこの時の発言で上院議員36人から憲法裁に提訴され、7月1日に首相職務の一時停止を命じられていた。
タイの憲法裁判所 ペートンタン首相の解職 命じる判断下すhttps://t.co/NEoAeHdZ7D #nhk_news
— NHKニュース (@nhk_news) August 29, 2025
ぺートンタン首相はタクシン元首相の次女。24年8月からタイ史上最年少の首相を務めていた。
後任は25年9月5日の下院首相指名選挙でタイ名誉党・アヌティン党首が選出された。同党は下院第3党で保守派政党の一つ。
首相解任はカンボジアとの国境紛争が引き金になった。
25年5月、タイ東部とカンボジア北部の国境地帯で両軍の銃撃戦が起き、国境検問所が封鎖されるなど緊張は一気に高まった。
7月に入って紛争は銃撃戦からロケット砲攻撃、戦闘機による爆撃と拡大、双方合わせて40人以上の死者が出る。両国は8月7日、マレーシアのクアラルンプールで国防相級協議を開き、東南アジア諸国連合(ASEAN)による停戦監視団設置などの合意文書に署名、紛争は一応の終息をみた。
タイとカンボジアは国境地帯にあるプレアビヒア寺院の帰属などを巡って長年対立していた。国際司法裁判所(ICJ)はカンボジアの提訴を受けて1962年に寺院、周辺の土地をカンボジア領とする判決を示す。タイ側はこの判決を拒否、両国軍による小競り合いが続いていた。寺院は9世紀末、クメール人によって建立されたヒンドゥー寺院で2008年に世界遺産に登録されている。
ぺートンタン首相は銃撃戦後の6月、事態打開を図ってカンボジアのフン・セン上院議長に電話、「おじさん」と親しげに語り、タイ軍幹部について「彼は反対派。彼のいう事は聞かないで」といった趣旨の発言をした。その音声が流出、首相はカンボジアにおもねっていると非難される事態になった。タイ側の対応を不満とするカンボジア側から流出したとみられる。
フン・セン上院議長は長く首相として国政を預り、息子のフン・マネット首相が率いる政権の後ろ盾となっている。タクシン元首相とも親交が深かった。
憲法裁判所の首相職務一時停止から解任までの判決は、国会での不信任議決などに基づくものではなく、完全な司法判断によってなされた。しかも、判決は最終的なものであり、上訴は認められていない。司法の政治への介入とも受け取られる判決は、現行制度上は問題ないとしても、立法と司法の独立性を著しく損ない、議会制民主主義のシステムを揺るがしかねない。強権の発動は「司法クーデター」ではないかとの批判を生む。
司法クーデターは今回が初めてではない。
19年11月、憲法裁はその年の3月の総選挙で野党第2党に躍進した新未来党のタナトーン党首が休業中のメディア企業の株式を保有していたとの理由で、議員資格を剥奪した。
20年2月には同党がタナトーン党首から多額の資金を受けたことが政党法違反にあたるとして解党を命じ、党首ら16人の政治活動を10年間禁止する。
同党は融資であり違法性はなく政治的動機に基づくものだと反論する。
若者らの支持を得ていた同党は軍事政権のトップから民政移管によって首相に転進したプラユット氏の政権を糾弾、国軍の予算削減などを訴えていた。議員資格を剥奪されながらなお根強い人気を維持していたタナトーン氏に脅威を感じた保守勢力が憲法裁に働きかけたと指摘された。
23年5月の総選挙でも新未来党の後継政党である前進党が第1党になったが、ピタ党首が半ば休止状態のテレビ局の株式を取得していたとして議員資格を剥奪され、同党にも24年8月に解党命令が出された。1週間後には当時のセター首相も実刑判決を受けた人物の閣僚任命が誠実性に欠けるとして解任されている。
憲法裁判所は最も民主的といわれる「1997年憲法」によって一つの独立機関として設立され、政権から独立した立場に立ち、政治家らの言動の説明責任を明確にさせるという目的があった。
民主的な憲法は政治と無縁ともいえた農民らの権利意識を目覚めさせ、タクシン氏を政治の表舞台に立たせた。タイ東北部のイサン地方を中心に農民らに支持を広げたタクシン派にバンコクを中心とする王党派、既得権益層、官僚らが強く反発、対立が生まれる。政治混乱を収拾するという名目で軍事クーデターも起きた。
憲法裁の権限はその都度、法律や選挙の合憲性の再審査、政治家と政党の適格性、政権転覆と見なされる行為の防止などへと拡大していった。
憲法裁判所の裁判官は9人全員が軍事政権時代に任命されている。
最高裁判所裁判官、最高行政裁判所裁判官らから選出され、上院の承認を必要とする。
上院議員は国民の直接投票ではなく、教育、農業など特定業種から選出され、各政党員の立候補は禁じられている。政権、保守勢力の意向が強く反映されるようになり、総選挙などで台頭した革新政党は政治制度の改革を求める活動などが憲法違反として抑え込まれ、社会変革の芽が摘まれていった。
憲法裁判所はまた、王制改革への試みを処罰対象として、刑法112条の不敬罪についての論議を封じ込める。
24年の前進党への解党命令も総選挙で不敬罪改正を訴えたことが政権転覆の動きにあたるという理由だった。判決は各党の不敬罪への取り組みを消極的にさせる。20年、若者らを中心に発生した反政府デモは不敬罪廃止、王室予算の削減などを訴えてバンコクから地方へと広がるほどの勢いを見せた。ハンガーストライキによって抗議する若者もいた。
いま、この問題を正面から取り上げる動きは聞こえてこない。
不敬罪廃止を求めた彼らの思いはどこにいくのか。(『アジア新風土記16、49、54』参照)
1997年憲法実施後のタイは、民主社会への歩みを確実なものにしているように感じられた。友人の一人は「タイ社会の民主化は東南アジアの先端を歩いている」と誇らしげだった。
約30年を経て、タイの社会は少しでも前に進んでいるのだろうか。限りなく後退したのではないか。タクシン派、保守勢力、国軍の三つ巴の対立が続くことで社会が不安定になり、憲法裁の判決はその不安定さを増大させた。
司法の「モンスター」がタイ社会を掻(か)き回している。
 ホーム
ホーム ご注文方法
ご注文方法 カートを見る
カートを見る お問い合わせ
お問い合わせ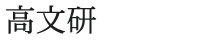
 関連書籍
関連書籍