- NEWS
高橋哲哉×徐京植 対談 他者の声 『奪われた野にも春は来るか』刊行記念
※この対談記事は、『奪われた野にも春は来るか──鄭周河写真展の記録』(2015年8月1日発行)の刊行を記念して、2015年9月16日、東京堂書店6Fホールで行われたトークセッションをまとめたもので、『詩人会議』2016年1月号に掲載された記事です。同編集部から記事のデータを提供していただき、転載いたしました。厚く御礼申し上げます。
徐 こんばんは、よくいらっしゃいました。多分いまごろ、参議院特別委員会では「安保法制」案を強行採決しようとしていると思います。こちらのトーク会場にいらしてくださってありがたい、とだけは私は思いません。やはりあちらで進行している事態も心にとめながら、しかしここではもう少し長いレンジ(尺度)で、過去から未来まで、思いを馳せて考えてみる機会になればと思っております。
2011年、3・11のあと半年ほど経った11月、韓国の写真家・鄭周河(チョン・ジュハ)さんと、韓国、平和博物館の歴史家・韓洪九(ハン・ホング)さんのお二方が福島を訪ねたいというので、私がご案内をして、高橋哲哉さんは福島のご出身でもあるので同行されて、鄭さんは撮影もされました。そこで出来た作品の展示は、最初は韓国でだけ行う予定でしたけれど、日本でもやろうということになって展示を始めました。
福島県南相馬市の市立中央図書館(’13年3月8日~10日)から始め、埼玉県東松山市原爆の図丸木美術館(同年4月16日~5月5日)、東京都新宿区ギャラリー「セッションハウス・ガーデン」(同年5月7日~16日)、沖縄県宜野湾市佐喜眞美術館(同年7月24日~8月26日)、長野県上田市無言館(=信濃デッサン館・槐多庵。同年10月27日~11月24日)、京都市・立命館大学国際ミュージアム(’14年5月3日~7月19日)にも巡回し、最終的に6か所で展示したのです。予想外に規模の大きな仕事になりました。その結果として、各地の会場で行われたトークを記録に残そう、それぞれ特徴があっておもしろいのではないか、ということになって今回の『奪われた野にも春は来るか 鄭周河写真展の記録』(高文研)という本になったわけです。
福島の原発事故をどう振り返るか
今日は福島の原発事故から4年半経って、事故をどう振り返るか、そして写真展そのものをどう振り返るか、というあたりから話を始めてみたいと思います。
高橋 こんばんは。私が徐京植さんと出会ったのはかれこれ20年前のことです。私にはそれまで在日朝鮮人の方の知りあいはいなかったのですが、徐さんの面識を得まして、いきなり二人でアウシュヴィッツを歩くという特異な経験をさせていただきました。
それから交流が始まって、90年代の後半に当時の日本と東アジアの状況をめぐって雑誌で対談をし、これを1冊の本にまとめる共同作業もさせていただきました(徐京植、高橋哲哉『断絶の世紀、証言の時代』岩波書店、二〇〇〇年)。それ以来私は、さまざまな問題に出会う度に、在日朝鮮の人びとからの視線、あるいは植民地支配の歴史、それらを踏まえてものを見る、ということを徐京植さんから学ばせていただいてきたのです。
福島の原発事故に際してもそういうことがありました。私は福島で生まれ育った人間ですし、福島第二原発が立地している富岡町というところの小学校に入学して、3年間そこに住んだことがありましたから、あの事故が起こった時はほんとうに大きな衝撃を受けました。
私だけでなく、福島の県民でも、日常的に原発を意識して生活していた人と言えるのは、おそらく立地自治体とその周辺の人ぐらいがほとんどであって、それ以外の人は日常的に意識するということはなかったと思います。
私は福島を離れてからだいぶ経っていましたが、自分の生まれ故郷であんな事故が起こるなど想像もしていなかったわけです。それだけ大きな衝撃を受けたのです。
その時に考えたことは、『犠牲のシステム 福島・沖縄』(集英社新書、二〇一二年)にまとめました。私は福島県自体が無くなってしまうのではないか、などと、しばらくは精神的なパニックに陥っていたようなところがありました。その時に、在日朝鮮の人をはじめとする日本人以外の人も同じように被災しているのだ、ということ、この事故が決して福島で起こった、日本で起こった事故というだけではなくて、日本人以外の被災者の問題があるのだということを、私自身すぐには思い浮かばなかったのです。
韓国の側からの問いかけ
最初に鄭周河さん、韓洪九さんらが来日されて一緒に福島に行ったときにまず訪れたのが、郡山市にある朝鮮学校でした。
私は大学に入って東京に移るまで、福島の地元に朝鮮学校があるということはまったく意識したことがなかったのです(福島朝鮮初中級学校一九七一年開校)。全くの盲点でした。そういう状況で、何人かで福島を訪れたのです。そこで朝鮮の詩人・李相和(イ・サンファ)の「奪われた野にも春は来るか」という詩を媒介にして、韓国の側から福島原発事故をどうとらえるかという、歴史的に射程の長い問いかけがなされた。私は大変深い印象を受けました。
その問いをどう受け止めるかをめぐって、鄭周河さん、韓洪九さん、そして徐京植さんたちと何度か話し合いを持ちました。その後、4年以上経っても日本では、韓国から「苦痛の連帯」をめぐる問いかけがあったこと自体、まだ共有されていません。これは非常に残念なことだと思っています。福島の現状についてはお話しすべきことはたくさんありますし、きりがないのですけれども、この人類史に残る事故が日本国内で風化しつつあるように感じられてなりません。
日本人は「フクシマ」とどう向き合ったのか、
の問いかけが共有されていない
あの事故が起こった時に、どこまで拡大するかまったくわからなかった。当時の首相官邸のなかでは菅直人首相や近藤駿介原子力委員会委員長、さらに第一原発の現場では吉田昌郎所長らが、いずれもこれは東日本壊滅の恐れがある、首都圏3千万、あるいは5千万の人間が避難しなければならなくなるかもしれない、などと考えて背筋が凍る思いをしていたということがあったのです。
そうならなかったのは、いくつかの偶然が重なった結果にすぎないのですけれども、いま日本ではそういう意識であの事故をみている人はほとんどいないのではないでしょうか。私は福島の事故はそこまで含めて考えられるべき事故なのではないかと思っているのです。
ですからもちろん二度とあってはいけないので、脱原発に向かって行きたいのですけれども、ご存じのようにいま安保法制を強行しようとしている安倍政権は、原発については脱原発とは正反対、原発推進政策に戻ってさまざまなことをしている。川内原発の再稼働などはその最たるものです。そういう意味では『奪われた野にも春は来るか──鄭周河写真展の記録』で私たちが考えた問い、〝日本人は「フクシマ」とどう向き合ったのか〟という問いがまったく共有されていないように思われるだけでなく、原発事故そのものがいま無理矢理過去に追いやられていくような状況にあるのではないかと思います。そういうなかで、ぜひとも私たちが考えた問いを共有していただければと思っています。
誰も責任をとらない
徐 では私からも一言申します。鄭周河写真展では、それぞれの場所で、場所柄を強く反映した、意味のある議論が行われたと思っています。
いろいろな論点のうちの一つは、植民地支配ということをどう考えるかということです。日本植民地時代の朝鮮人詩人の詩をあえてタイトルに冠した写真展ですから、当然そのことは重要な論点として意識にあります。
もう一つはああした事故を表象、表現することは可能か、可能だとすればいかに可能か。原発事故、戦争、大災害などのような事件とその表象とをめぐる問題です。とくに無言館のトークではそういう議論が出ました。これも大きな論点の一つです。さらに、いま高橋さん自身からもだされた日本の現在の政治状況とか、近現代の政治的な構造のなかで「フクシマ」をどうとらえるのかという問題、あるいは東アジアの政治状況のなかでどうとらえるのかという問題も当然あると思います。
明治以降の日本が過去にならない
私は事故の直後、2011年4月から韓国の媒体に自分の文章をだして、いま思えば精神的に慌てていたところもあるので、かなり思い切ったことをいろいろ書いたのですけれども、そこで述べたことの一つは、この事件が日本の再ファシズム化の転機になるだろうという見通しです。「事故を過去に追いやる」というように高橋さんはおっしゃったけど、逆に言うと、ネガティブな意味での「日本」は過去にならない。だから「過去にならない日本」というタイトルの文章も書きました。奇しくも安倍さんは「日本を取り戻す」というスローガンで政権に復帰したわけです。だから、過去にならないというのは、別に3・11の前か後かだけではなくて、明治初年以降の日本が少しも過去にならない、ということがもう一度証明されたということです。
それから、日本でいうと原子力ムラ、韓国で言う原子力マフィア、そういう癒着の構造ですね。同時に無責任の構造。誰も責任をとらない、ということを、まあ予感はしたのですけれど、はたせるかな4年半経って誰も責任をとらないままです。それどころかますます居直っているという現状が目の前にあります。
抗いがたいような流れのなかで抗おうと発信した人たち
日本の右傾化とか、ファシズム化という危機は、昨年以降非常に表面化してきました。現在行われている安保法制反対の闘いは、それをどうやって防ぐか、防ぎうるかどうかという闘いです。これは少しも誇らしいことではないのですが、原発事故が起きた直後に私が感じたネガティブな予感は、「ほらみろ、おまえが神経過敏だっただけで、現実はそうならなかったではないか」とはならず、私自身の予感をも上回るかたちで的中しつつある、そう思っています。
こういう写真展、たかだか写真展が、そういう流れを阻みうるような力になるとは思ってはいないのですけれども、しかし本のあとがきに書きましたように、こういう大きな抗いがたいような流れのなかにも、それに抗おうとして発信した人たちがいたのだということは記憶されていいし、それこそいつか、私の時間尺度でいうと、数十年後であれ、あるいは百年後であれ、その発信に目を止めてくれる人がいればいいのだがという、そういう気持ちもありました。
ちなみに、これも写真展の副産物ですけれど、私と高橋さんと韓洪九さんという三人で、済州島とか沖縄とかをまわって各地で行った座談会の本が平凡社からでております(『フクシマ以後の思想をもとめて 日韓の原発・基地・歴史を歩く』)が、日本でよりも韓国で、より多く読まれています。原発事故が国境を越えるものであるように、この発信は、発信した本人たちにもわからないようなかたちで、わからないようなところで、誰かが受け止めているかもしれない。受け止めているにちがいないと、確信し希望をもつ根拠はないけれども、そうであってほしいという気持ちでいるわけです。
敗戦時の構造と同じ構造の反復
次の話題に移るための問題提起として申しますと、私は誰も責任はとらなかったという構造は、実は日本の敗戦時と同じことが反復されたと思っているのです。あれほど大きな災害があったのに、というだけではなくて、それの起こり方もその「収拾」のされ方も、また「コントロールされている」という虚言、その虚言に、国民の多数が虚言であることを知りながらついていく状況。そのことも、日本の敗戦時の、いわゆる戦後復興の神話の構造を反復している。だから、つまり1945年と、2011年に起きたことは、そのあいだにいろいろ同様のことは起きているわけだけれど、まったく反復されていると思うわけです。
そこのところを抉り出して乗り越えることができるかどうかが、ほんとうは原発事故が投げかけた問いです。それが、どうやって収拾できるかとか、復興できるかということ以上に根本的な問いだ、と私は思っています。いちばんわかりやすいのは、このことが起きた後に、他者に対する責任の表明とか謝罪が一言もないということです。
日本が敗戦したときは、日本の戦争によって被害を与えた相手、殺した相手に対して「悪かった、申し訳なかった」という思いから出発すべきでしたけれど、それはありませんでした。
被害を他者に対して詫びるという発想がない
福島も同じです。福島も、国策によって原発を推進し、ある企業とか、原発ムラが、利潤をはかるためにやってきたことでしょう、その結果、大きな被害を他者に与えた。それは他国民、多民族というだけではなくて、地球環境に大変な被害を与え、向こう百年、二百年、あるいはひょっとしたら数万年、消すことのできない損壊を与えた。
それについて「申し訳なかった」「悪かった」と、人類に対して詫びる、被害を与えた他者に対して詫びるという発想が少しもないのです。政府や東電にその発想がないけれども、これはちょっと辛辣すぎる言いかたかもしれませんけれども、日本国民の大多数のなかにも、自分たちが受けた災難という発想はあっても、自分たちの国家が他者を害したという発想がどれくらいあるか。それを考えると、これはやはり日本は変わらない、変わらなかった、そのネガティブな面だけがむしろ純化されてきたな、という感じを私はもっているわけです。いかがでしょうか。
高橋 いくつも問題をだされましたし、いわゆる植民地支配、あるいはもう少し一般的に言うと、植民地主義、コロニアリズムの問題というものが、この本のなかではかなり根本のところで問われているわけです。
私自身『犠牲のシステム 福島・沖縄』のなかで、植民地主義という言葉を使って福島と沖縄を比較してみたことがあり、また「奪われた野にも春は来るか」という韓国からの問いかけでは、韓国に対する日本の植民地支配と、福島の事故での加害、被害の関係とが重ね合わされて、重ね合わせることができるか、ということを含めた問いかけとなってでてきているので、言ってみればここに、日本国家と朝鮮、沖縄そして福島という三つの関係、それぞれが、なんらかの意味で植民地主義的な支配関係ではなかったのかということが、本題として問われているのです。
植民地支配の問題
朝鮮に対しては、当然植民地支配だった。言うまでもないのですが、沖縄に対しては、私は当然そうだったと思い、現在もまだ植民地支配が続いているとさえ思っていますけれども、この認識は必ずしも日本のなかで一般的ではありません。
沖縄ではいま、辺野古新基地建設に対する日本の政府や有権者の態度をみながら、いまなお植民地支配が続いているのではないかという意識が高まっていますけれども、この認識はまだ日本のなかで一般化されてはいないわけです。
福島に対して植民地主義という言葉を使えるかどうか。これについてはかなり強い疑問も出されています。朝鮮に対しては、明らかに、日本という異民族の国家が大韓帝国を併合して朝鮮民族を支配した。沖縄も、琉球王国が存在したわけですけれども、これを併合して、同化を進めていった歴史があるわけです。
しかし福島については同じようなことが言えるだろうか。これは確かに同じだとはまったく言えないわけです。にもかかわらずそこに、なんらかの植民地主義的な支配関係があったのではないか、という問いが立てられた。
鄭周河写真展の記録に出てくる、沖縄での写真展に際して開催されたシンポジウムのなかでは、福島と沖縄とはまったく違うという批判が、沖縄の比嘉豊光さんという写真家の方からありました。ここではとりあえず、そういう問題が議論されているということを申し上げておきたいと思います。
もう一つは、いま徐さんから非常に厳しく問われた責任の問題です。敗戦のときとまったく同じことが繰り返されたのではないか、と言われましたが、私も同感です。福島の原発事故のときに、これは第二の敗戦ではないかという言い方が期せずして出てきましたが、私もそのように捉えてきました。国策に対して国民がなかば盲目的に従ってきてその結果、大きな破綻に至ってしまった。その後も責任の所在がまったく曖昧にされたまま、放置されている。徐さんはいま、多民族、他国に対する責任の表明がまったくなされなかったという点でも同じだとおっしゃいましたけれども、これは国内に対しても同じことが言えると思うのです。
原発の恐怖から免れて生きる権利をうちだす訴訟
丸山眞男の「無責任の体系」という有名な議論があります。日本の近代国家のシステムは天皇制と言われますが、これは「無責任の体系」なのだと。これはまさにアジア・太平洋戦争の敗戦に際して指摘されたわけですけれども、今回も電力会社、政府、いずれもその幹部たちは責任をとらずに今日まできている。責任を追及しようという動きはあります。福島の武藤類子さんたちを中心とした告訴団が刑事責任を追及しようとしていますけれども、なかなかまだ結論はでていないし、非常に厳しい状況だと思います。
電力会社、政府だけではなくて、原発施設を作った原発メーカーの責任も重大ではないかという指摘も出ているのですが、日本の法律では大事故が起きても原発メーカーはまったく免責されるかたちになっている。電力会社が無限責任を負うわけです。これではおかしいのではないかと、原発メーカーを対象とする訴訟が起こされて、ノーニュークス訴訟というものですけれど、ノーニュークス権、原発の恐怖から免れて生きる権利というものをうちだしていますが、これもまだどうなるかわからない。日本の国家がこれまで戦争責任、植民地支配責任に対してとってきたきわめて頑迷な拒否の態度というものにどれだけ風穴を開けられるか。未だ不透明な情勢です。
昭和天皇が戦争責任について述べた言葉
私は第一の敗戦(アジア太平洋戦争の敗戦)の時の、戦争責任、植民地支配責任の問題について言えば、1975年の10月31日、日本記者クラブ記者会見で昭和天皇が述べた言葉に尽きるのではないかと思っています。みなさんどの程度ご記憶かわからないのですが、昭和天皇がアメリカ訪問から帰ってきて、はじめての記者会見を皇后といっしょに行なったときに、記者のなかから、「陛下はいわゆる戦争責任についてはどのようにお考えですか」という質問がでました。このときにどういう答えをしたかというと、「戦争責任というような言葉のあやについては、私は文学方面についてはきちんと研究していないので、答えかねます」と。
戦争責任というのを〝言葉のあや〟と称して、それで記者会見がすんでしまった。このことにすべてが集約されているのではないか。天皇がそのような発言をして、なおかつ日本社会のなかでそれが大問題にならなかったのですね。同時に「広島、長崎の原爆投下についてはどのようにお考えですか」という質問がでて、これは「広島市民には気の毒ではあるけれども、戦争中であったのでやむをえないことと考えています」という答えだったのです。これがかろうじて新聞の見出しになって、被爆者団体から違和感の表明がありましたが、〝言葉のあや〟のほうは見出しにすらならないのですね。これは驚くべきことだと思います。
つまり戦争責任の最高責任者がそのような発言をして、なんら責任を問われずにすんでいる。日本社会そのものが、責任を追及できないということですね。この構造がいまもなお続いているような気がしています。ここに、繰り返し考えるべき問題があるのではないかと思っています。
いま大詰めに来ている安保法制の国会審議ですけれども、ここで出てきている日本政府に対する市民の抗議、あるいは反対運動というものがどこまで歴史的な射程というものをもって、これから思想的に深められていくのか、これも問われている気がします。
徐 私もいま高橋さんがおっしゃったことをよく記憶しているのですけれど、茨木のり子さんが、
戦争責任を問われて
その人は言った
そういう言葉のアヤについて
文学的方面はあまり研究していないので
お答えできかねます
思わず笑いが込みあげて
どす黒い笑い吐血のように
噴きあげては、止まり、また噴きあげる
というように、直截に天皇のその発言を批判する詩を書かれました。(「四海波静」より)
しかし大多数の戦後派詩人、戦争経験をもっていたはずの、おもに男性詩人たちはスルーしました。ですからこれは文学史上の問題にもならなかったのです。政治的な問題にならなかったというのは、政治権力との力関係上、そういうこともあったということが、ひょっとしたらエクスキューズ(言い訳)として言えるかもしれないけれど、文学上の問題にもほとんどならなかった。つまり、詩人や文学者の感性もこの発言を「スルー」してしまった。そのことを、いまお話を聞きながら思い出しておりました。
天皇制護持、日米安保条約、憲法九条の三点セット
天皇制の国体護持、日米安保条約、憲法九条が、三点セットで、戦後の構造としてつくられたわけです。つまり日本は武装しない、しかし天皇制は残してやる、その代り日米安保で義務を果せということです。しかしそのことの具体的な負荷は、やがて沖縄に集中することになっていく、そういう三点セットです。その三点セットとしての戦後構造は、七〇年経って少しも過去にならない、ということだと思います。
国民が自分と国家を癒着させている
ですからそこで、在日朝鮮人として私の立場から端的に言うとすると、日本国民のみなさんいつまで国家の共犯者で居続けるのですか、ということです。国家は国民のみなさんを共犯者に引き込んで、そしてある場合には利益を配分するけれども、多くの場合は戦争中と同じで、受忍論です。東京大空襲とかでも戦争中だから国民は辛抱すべきだ、受忍論というかたちで国家は補償をしないということがまかり通っている。そういう国家です。つまり国民のみなさんが、自分と国家の関係を癒着させているから、国家が犯罪を行った場合にそれを追及できないという構造が、ずっと存在してきて、いまもあるということです。だから抱きしめられながら、共犯者にさせられてしまう関係をいつまで続けるのですか、ということです。
被害者に向けての言葉がない安倍首相の七〇年談話
これから沖縄の話になりますが、沖縄は、日本国家とのそういう関係はもう嫌だと自覚しはじめ、そのことを発信し始めたのだと思います。安倍首相が8月14日、戦後七〇年の談話をだしましたが、あれ自体が論外なシロモノで、第一次世界大戦後の世界の流れのなかで進路を誤ったという話です。それすらも心から反省しているわけではなく、まして日露戦争については肯定する立場から述べています。
しかし日露戦争は朝鮮植民地化の戦争でした。その前の、台湾植民地化について安倍談話には一言もありません。それ以前の、琉球の併合についても一言もありません。それから、アイヌモシリ、北海道についてもそうですね。つまり、日本が進路を誤ったのはこうした周辺諸民族への侵略と植民地支配の始まりからなのであって、別に第一次世界大戦以降のことではない。彼が進路を誤ったというのは、世界の帝国列強のなかで、自分たちの位置を、より少ないコストで占めていくことにおいて進路を誤ったという話に過ぎないわけで、他者との対話になっていない。被害者に向けて語る言葉ではないのです。
多くの日本国民がそのことをわかっているだろうか。日本のマスコミ等がそのことを正確に指摘しただろうか。そういう指摘が、中国なり韓国なりアジアからでてきたときに、ナショナリズムにとらわれた発想であるとか、あるいは日本に対する劣等感だとか、「反日だ」というような言説によって、他者のほんとうの声を聞こうとしないということが反復されるのではなかろうか。
沖縄の基地は「本土」が引き取るべきだ
高橋さんは最近『沖縄の米軍基地 県外移設を考える』という本を集英社新書からだされて、大変チャレンジングな主張をされました。つまり沖縄の基地は「本土」が引き取るべきだという主張です。これについてはその通りと賛成する人と、当惑している人がいると思うのですけれども、簡単に高橋さんからその真意と言いますか、そういうお考えに到達するに至った経過をお聞きしたいと思います。
高橋 はい、わかりました。その前に、徐さんがいま言われたことで……
徐 三点セットのことですね。
高橋 そうですね。ただその前に、第一の敗戦、第二の敗戦に通底する構造ですが、少しも過去にならないものということがある。というのは、過去に向き合えない。起こったことに向き合えない日本が少しも過去にならない。もちろん起こったことというのは、起こっているときにこそそれを変えなければいけない。これは戦争にしても、植民地支配にしても、原発にしてもそれが現に起こっているときに、それを変えなければいけない。それは当然なのですが、敗戦、原発事故、大きな破綻をきたしてしまったときに、その起こったことに向き合えない。
過去に向き合えない日本が過去にならないでずっと続いていくと、そう言えるのかなと思いました。
天皇と国民の関係が変わったのか、変らないのか
戦争責任の問題から現在の安保法制をめぐる問題まで、最近、辺見庸さんとあらためて対談をしました。辺見さんは最近『週刊金曜日』に「1937」という文章を連載されていたのですけれども、これは1937年つまり当時の支那事変、日中戦争が全面化した当時の、ひいては日本の戦争の歴史全体をあらためて問いたいということで書かれたものなのです。
そこに東京大空襲のときの話がでてきまして、大空襲というのは、一晩で10万人ぐらいの犠牲者がでたというので、広島や長崎に匹敵する犠牲がでたわけです。数日後に昭和天皇がその現場に行ったわけです。写真も残っています。そこに被災者がいるわけですね。辺見さんが言うには、その被災者は、ちょうど「言葉のあや発言」がでたときに茨木さん以外はほとんど誰も、それを厳しく追及しなかったということですけれど、ほんとうであれば、天皇の胸ぐらをつかんでですね、なんでこんなことになったのか、おまえの責任じゃないか、そういう人がなぜ一人もいないのか。そこで被災者たちはみんな土下座をして天皇に謝っているというのです。
そのことと同じかどうかわかりませんけれども、福島の原発事故のときに、非常に興味深いことがありました。菅直人首相が被災地を訪れたときに、これはかなり厳しい叱声にさらされました。「もう帰るのか、われわれをどう思っているのだ」と被災者から追及されました。
しかし、天皇皇后が行ったときには、被災者は涙を流してこれを喜んだ。これはぜひ私たちが考えるべきことかと思うのですが、戦後の象徴天皇制の役割、あるいは天皇と国民の関係が、どの程度変わったのか変わらないのか、ということにもなるのではないか。辺見さんとの対談でそのことを思いました。
沖縄に押し付けられた安保条約
沖縄については、『沖縄の米軍基地 「県外移設」を考える』という集英社新書を新しく上梓しました。これは最初に申しました『犠牲のシステム 福島・沖縄』という本を出したときに、基本的にはすでにそこで言っていたことなのですが、沖縄は戦後の日米安保体制のなかで、犠牲にされてきたわけです。沖縄に米軍基地を集中させることで、日米安保体制が成り立っている。そういう意味で日米安保体制は沖縄を犠牲とする、犠牲のシステムだったという認識。これは3・11より前に私自身は思っていたのですけれども、原発事故が起こったので、両者を並べて比較することをまずやってみた。そして今回は沖縄の問題に集中して、沖縄以外の日本のことをなんと言ったらいいかわからないのですが、「本土」という言い方はすでに日本中心主義的な、植民地主義的ないい方だとも言えるので、カッコつきで言わなければいけないのですが、「本土」が沖縄にどう向き合えばいいのかということを考えてみたわけです。
私は、沖縄の米軍基地は日米安保体制のもとでは、本来「本土」に置かれるべきものが沖縄に集中させられていると考えています。これには二つの側面があって、一つは構造的な側面で、すべての米軍基地は日米安保条約に基づいて置かれているわけですから、1972年に沖縄が日本にいわゆる「復帰」をした後は沖縄の基地も安保を根拠として置かれている筈です。
しかしこの日米安保条約自体が、1951年に締結された時も、60年に改訂された時も、沖縄の人の民意はまったく反映されていなかった。沖縄出身の国会議員は一人もその時国会にいない。そういう状態で締結され、また改訂されてきているわけです。ですので、安保条約も沖縄に対しては押しつけられたものであるわけです。
安保条約の支持率
現在、安保条約の支持率は驚くなかれ、9割近くに達しています。今年の5月6月に共同通信社が行なった世論調査では、日米同盟を強化すべきだ、が20パーセント、維持すべきだ、が66パーセント、あわせて86パーセント。日米同盟を解消すべきだ、というのはもう2パーセントしかいない。こういう状況なのです。他の世論調査を見ても、2010年代に入ってからは、日米安保支持率は8割台に達してきているわけです。
このなかで沖縄の人は、人口が1パーセントしかないわけですから、全員、安保を支持したとしても1パーセントしかそのなかに入らないわけですね。ですから安保支持というのは、ほとんど「本土」の人間がこれを支持しているわけです。
ところが、その安保条約によって置かれている在日米軍基地の74パーセントは、わずか0・6パーセントの面積しかない沖縄に集中させられている。私はこの構造自体が非常に不平等だと思いますし、沖縄からの問いかけはこの間つねにそこを問題にしてきたのです。
沖縄の米軍基地の責任はどこにあるのか
「本土」が安保条約を維持したいというのであれば、当然その基地は、「本土」が負担すべきであって、なぜ沖縄に押し付けられるのか。ですからいま、辺野古の新基地建設が問題になっていますが、もちろんこれは断固阻止しなければいけない。けれども、辺野古を阻止すればそれでいいのか。それだけの問題ではまったくないわけです。沖縄にある米軍基地すべてが、安保条約のもとでは日本に置くべきものだという、これは米軍基地に関する責任主体の問題です。沖縄の米軍基地の責任はどこにあるのかという問題です。
もう一つは、歴史的にみて、なぜ沖縄に集中させられて来たかというと、1950年代から、「本土」にある米軍が沖縄にどんどん移駐させられたということです。海兵隊はもともと「本土」にいたのが、沖縄に行ったのです。本のなかに書きましたけれどもそれ以外にもいくつもあるわけです。沖縄から米軍が撤退しようという機会が何度かあったのですけれど、日本政府がそれを抑えたのです。それから、野田政権の時ですが、沖縄の海兵隊1500人を岩国に移駐しようというアメリカ側の提案があった時には、日本政府がこれを断っているのです。
日米両政府は、要するに日本本土に米軍基地を置くといろいろ問題が生じるので、沖縄に基地を隔離している。圧倒的多数の日本国民の目から基地が見えないところに隔離して、これを維持していこうと考えたのです。こういう構造的、及び歴史的な理由から、私は安保体制下においては、本来沖縄の基地はすべて日本が引き受けるべきもの、引き取るべきと思います。では引き取ってどうするのか。私は安保条約は解消されるべきものだと思っていますが、これは現状では非常に困難かもしれません。なぜなら8割9割がそれを支持しているわけですから。しかし、アメリカに対する底なしの従属関係、これは日本に主体性がまったくないというわけでは決してないのですけれど、むしろ自発的にアメリカに隷従していって、それによって利益をえようとする。そういう構造がずっと続いていることが問題です。
精神のなかにある植民地主義、
多数者のなかにある無意識の植民地主義
私はやはりアメリカに依存するのではなくて、これは朝鮮半島、東アジア全体の問題にも関わってきますけれども、アメリカなしで東アジアの諸民族、あるいは国家同士が安全保障の秩序を作っていくべきだと考えますし、日米安保体制というのは、日本が米軍の戦争に加担してきたことを意味すると私は認識していますので、そういう意味で日米安保体制はいずれ解消されるべきものだと思っています。それは、本来「本土」に置くべき基地を「本土」の人間の責任で安保を解消することによって撤去する、すべきだということなのです。
徐 高橋さんが最初におっしゃったように、私と高橋さんがこうしてお話しするようになって、20年経つのですね。90年代の中ごろです。世界的にはちょうど記憶の問題、日本では高橋さんたちが、ナチ強制収容所生存者のインタビューを中心にした、クロード・ランズマン監督の「ショアー」という記録映画の上映運動されたことが知り合ったきっかけです。
第二次世界戦争の記憶を、どのように私たちがもう一度記憶すべきなのかということが当時問われた問題です。しかしそれは抽象的に問われたのではなく、アジアの戦争被害者たち、いわゆる「慰安婦」日本軍性奴隷の人たちが名乗りでて、それに日本社会、日本国民、日本国家がどう向い合うべきかという問いと重ね合わせて問われたことなのです。けれど、この問いをめぐる議論は噛み合ったとはいえず、私自身の立場からみると、とても多くのフラストレーションを感じてきました。その原因の一つは、自国が行った植民地支配という問題意識、それから他者に対する認識が、多くの日本の、いわゆる進歩的知識人のなかにも欠けているということです。
つまり、今回の著書で高橋さんが主張されたようなこと(一般化すると植民地支配による被害者の側の自決権支持)を言うと、たとえば、それは「本土」の沖縄化を結果するだけではないかとか、本来の原則的な平和主義を放棄するのかとか、そういった普遍主義的な言説による反発をかうことになるわけです。
そういうように批判する人たちは、原則的平和主義という、ある種の倫理的高みに自分がいるかのように語る。同じように、日本軍「慰安婦」など韓国の植民地支配被害者たちの主張は、ナショナリズムにとらわれたものだなどという。それを言っている本人は、あたかも自分自身はナショナリズム的な発想からは自由であるかのような立場から述べるのです。いうまでもなく、この人々のナショナリズム批判は、何よりもまず、自国に向けられなければならないはずです。植民地支配と侵略戦争の歴史を否定し、被害者への謝罪と補償を拒否し続けている自国に。
そこに他者がいて、その他者が、現に存在している構造によって日々損なわれている。その人たちが自らの権利を主張している。そういう構造は自分自身が意図的に押し付けているのではない場合でも、すくなくとも自分が主権者として属している国家が押し付けているものである。ならば、主権者としての自分はどういう選択をすべきなのか。そういう問題に対してその普遍主義的高みに立っている人はどういう位置を占めているのかが、問われない、あるいは無限に先延ばしされる。その結果、現にいる弱い立場の人たちに絶えずそのしわ寄せがいく。そういうことが繰り返されてきた。
もちろん女性差別と植民地支配、あるいは朝鮮植民地支配と沖縄の問題は違うけれども、そこには一つの共通する構造がある。それは名付けると、精神のなかにある植民地主義、多数者のなかにある無意識の植民地主義である、そう思います。
植民地支配の責任についての発信
もちろん福島と沖縄は違う。朝鮮と沖縄は違う。違うのですけれども、これは比喩です。比喩というのは違うものだから比喩するのです。AとBが同じならAのようなBという比喩は成り立たない。AとBは違うからAのようなBという比喩が、ある人たちに忘れていたことを思い出させるとか、気付かなかった点に気付かせるといった効果を発揮するわけです。
そのように考えると、沖縄の基地問題はやはり福島と通底しています。つまり原発というものの脅威とか危険性を東京以外のところに押し付けて、電力だけは消費して、そして事故が起きても、あれは福島で起きていることなのだ、東京は大丈夫ということだけを話してやりすごし、従来通りの無責任構造を維持し続ける。
つまり、(植民地時代の朝鮮がまさにそうであるように)沖縄なり福島なり、ある地域、ある民族、あるいは女性や少数者を絶えず周縁化しながら、その周縁部に問題を押しつけておいて、中心は大丈夫だという構図の言説をつくり、そこに多数者を引きこんでいくということです。つまり中心部による周縁部への差別を利用する支配構造であり、中心部の人々も自らが周縁化され差別されることを逃れようとしてその構造にすすんで従属していく。そうようにして、本来は被害者である人たちまでもその構造に引きこまれて、国家との共犯関係に陥っている。私はそう思うのです。
ですから高橋さんはこの日本社会においてきわめて希(まれ)な人だと思います。いま彼が主張していることはこれから大きな議論を呼ぶと思うけれども、植民地宗主国中心部にいる知識人が、自ら植民地支配の責任について、このように発信するということは、世界的にみてもかなり希だと思います。
それは植民地被支配者、被害者の側からの、粘り強い指摘を受けながら、長い時間かかって作られていく認識みたいなものです。まさに対話の産物ともいえますね。私はそういう意味で、高橋さんの一歩踏みだした主張は、戦略や戦術として今後どうすべきかという運動論的なことはいったん別としても、問題の本質についての指摘としてはきわめて重要だと思います。これは運動論的な次元の提案ではなく、より原則的な植民地主義批判なのだということです。
ですからみなさんも、戦術、戦略的な基地引き受け論対、原則的な平和主義との対立構図としてとらえると、これはまったくずれた認識になってしまします。そうではないです。根本的には沖縄という場所、あるいはそこの人びとを他者として認識できるのかどうかという問いなのです。そこをどうすべきかを決める自決権をもつ当事者はその人たちなのです。ところが植民地支配の結果、長い間沖縄の人たちの多数もそのように日本国民化される経過を辿ってきたために、「国民は共に受忍しよう」という言説が当たり前のようになっていた。ここには見えやすい欺瞞が隠されています。まず、「共に受忍」というが、「本土」と沖縄の関係は基地負担ひとつをとっても決して平等ではない。さらに、沖縄の人々は植民地支配によって「日本国民」の枠に引き入れられたのであって、もともと「同じ国民」ではない。他者なのです。他者の尊厳や自己決定権を基本的に尊重できるかどうか、他者として認識したうえで新たに連帯の道を歩めるかどうか、そういう重要な問題がここに提起されていると私は思うのです。どうでしょうか。違っていますか。
差別は人間の尊厳にかかわる
高橋 私はこの主張を発信するにあたってやはり覚悟が要りました。特に私の親しい人たちが、どういうふうに反応してくれるか不安はあったのです。いまのように徐さんに言っていただけると、とてもうれしい。私の狙いとするところを徐さんのポジションから言っていただいたように思います。
少し違った言い方をしますと、要するに反戦平和と植民地主義あるいは差別の問題で、これが絡み合ったところで起きている非常に難しい問題なのです。ですから私の主張が、そんなに簡単に受け入れられるとも実は思っていないわけです。徐さんがいま最後に、普遍的な問題と戦術的な問題とおっしゃいましたけれども、実際、基地引取り論、あるいは県外移設論は戦術としては理解される。安保を支持するというのはそれだけの負担とリスクがあることなのだということを、日本のマジョリティ(多数派)に知らせるショック療法として、戦術としては意味があるけれども、普遍的には反戦平和のほうが大事なのだという議論があります。現に沖縄の知識人のなかにもこれはあるわけです。ただ私の考えでは、では反差別という原則は普遍的ではないのか。どうでしょうか。私は差別というのは人間の尊厳に関わる問題だと思いますから、単なる戦術で反差別というのはおかしいのではないかと思います。
差別をしたままで反戦平和を唱え続けていいのか
私が問題提起したことは、言ってみれば反戦平和という理念を差別的な構造を続けたまま、言いつづけることができるのかということなのです。差別をしたままで、反戦平和を唱え続けていいのかという問題になるわけです。反戦平和の立場からすれば、基地は沖縄にいらないし日本にもいらない。軍事基地はすべて反対だ。これは当然原則になるわけです。普遍的な理念であるわけです。これはとても大切なので、私は先ほども言いましたけれども、目標としてはあくまでも堅持しているわけです。しかしその理念を沖縄の人に対して言うと、これは県外移設を拒否する論理になってしまうのです。
沖縄にいらない基地は「本土」にもいらないと言ってしまえば、沖縄の人が、では安保を支持するなら、安保を支持しているのは「本土」の人なのだから、基地を引き取ってください、という議論を封じることになってしまう。つまり差別的な構造を残してしまう。私は差別を続けながら、植民地主義的な支配被支配の関係を続けながら、反戦平和を言いつづけることはもう無理なのではないかと思うのです。
徐 反戦平和という普遍的な理念そのものの、真価というか、覚悟というか、深みというか、それが問われているのだと私は思っていて、つまり一部の、それも19世紀になって併合した植民地地域の人びとの負担の上に立っている理念は果たして普遍的なのか。その人たちの負担コストによって、その人たちに負担を強いている側が自分は普遍的な理念の側に立っていると言えるのかということだと思います。思想的な試練をくぐらなければ、それは普遍的なものでも何でもなくて、きびしい言い方ですけれども、虚構の平和主義です。戦後日本平和主義の虚構性がいまここでもう一度問われていると私自身は思っているのです。少し突飛な比喩ですけれど、その言葉を誰がどういう文脈で誰に向かって言うかということがとても重要で、たとえば沖縄の方が「私は世界中の誰にもこんな負担を負わせたくないから、もちろん県外に移設してほしいけれども、「本土」に引きうけてくれということも言いたくない」と言うとします。立派な発言だと思います。しかしそれは立派だからそれやってください、と「本土」の人間が当然のように要求することは図々しいことだと私は思います。
このことは私に、ハンナ・アーレントの言葉を想起させます。
〈何年も前から私は、自分がドイツ人であることを恥じるという何人ものドイツ人に出会ってきた。私はいつも彼らに向かって、私は人間であることを恥じると答えようという思いに駆られた。この原則的な恥ずかしさは、今日では様々な国籍の人間が共有するものであり、感情の上で国際連帯に関して残された唯一のものである。〉(「組織化された罪」『パーリアとしてのユダヤ人』)
「ホロコースト」が進行中であった第二次世界大戦の末期、亡命地アメリカで書かれた文章の一節です。
ある人がアーレントに向かって自分はドイツ人であることを恥じると言った。アーレントがユダヤ人であり迫害を受けて亡命してきたことを知っているからです。するとアーレントは、私はむしろ人間であることを恥じると答えようとしたという話です。まさしく「普遍的理性」の表明といえるでしょう。しかし、この同じ話法を、その時点で、ドイツの人たちが使ったとしたらどうでしょうか。自分が「ドイツ人」であることが恥ではない、私たちは(ドイツ人であれユダヤ人であれ)人間として恥ずかしいのだから、と。そう言っていいでしょうか。それは亡命ユダヤ人であるアーレントだから言えることであって、ユダヤ人を迫害し虐殺しているドイツという国の国民の側は、たとえ被害者の側がそういってくれても、やはり胸を張ることができない責任感を感じていると答えることが正しいのではないでしょうか。それと同じような構造がここにあると私は思います。たとえ沖縄の人々が広大無辺な普遍的理性に立って、基地負担を「本土」に押し戻さないと言った場合でも、「本土」の側がそれを当然のこととしてはならない、ということです。
受益者である一方で普遍的な理念をとるダブルスタンダード
つまり普遍的な理念は、普遍的な場所にあって、誰でもが無責任に自由にとってきて食べていい果実ではないのです。それをとってきて食べるためにはなぜそこにそれがあるのか、誰の負担によってそれがあるのか、自分はそれを食べていいのかという内省を伴って初めて可能なのだと思うのです。ですから、沖縄の問題、朝鮮のことにしろ、あるいは原発その他さまざまなことにしろ、一方で受益者でありながら一方で普遍的な理念を標榜することは明白なダブルスタンダードです。自分たちだけは実利(あるいはその幻想)を享受しながら、他者に不利益を押し付け、高邁な普遍的理念を標榜してそのことの欺瞞性から目を背ける。このダブルスタンダードをついに日本社会は抜けることができないのか。
こうしたダブルスタンダードと、原子力ムラのような無責任構造が続き、福島の事故はアンダーコントロールだという虚言に国民大多数がついていくという構造は相互に奥深く結びついています。私はそう思っているので、もちろん実際の運動論の次元ではいろいろな議論があっていいと思うけれども、高橋さんの今回の提案はとても重要な、深く議論すべき問題だと思っています。
高橋 いま徐さんがハンナ・アーレントの例をだして説明してくださったことですが、具体的に沖縄の例で言うと、1995年の少女暴行事件があった時に、沖縄で反基地の感情、運動が高まりました。その時に大田昌秀県知事が、「本土」の人間が安保を維持したいのであれば、応分の負担をすべきだと言ったのです。ただ、自分たちの痛みを他人に移すのは忍びないという沖縄のこころというのがあるので、本土移設までは自分は言わない、と。
いま翁長雄志県知事がときどき言うのは、果して沖縄が日本に甘えているのですか、日本が沖縄に甘えているのですか、ということです。日本が沖縄に甘えるというのは、そういう沖縄のこころに甘えているということだと思いますから、もはや甘えることは許されないということなのです。
それからもう一つ、徐さんが最後に言われたことをいまの状況に絡めて言えば、いま安保法制反対の運動が高まっている。一方ではそれを強行採決して突破しようとする政権の動きがある。非常に緊迫した状況ですね。私はもちろん安保法制には断固反対なのです。しかしここでいま、安保法制反対の運動が高まっているその内実はどうなのかということは、やはり思想的に検討されるべきことだと思います。
シールズの若者とか、新しく運動に入ってきた人、はじめて声をあげた人、それはすぐにそうはいかないかもしれないけれども、ではその、戦後に彼らがあるいは私たちが守ろうと、守るという言い方が果してできるのかどうかもありますが、守ろうとしている戦後日本のカッコつき平和というものは、その内実はなんなのかということです。
安保体制そのものを問わなければいけない
安保法制に反対の人は相当のパーセンテージにのぼっているでしょう。しかし、先ほど私がご紹介しましたように、日米同盟を支持する人が8割9割いるのです。これをどう考えるのかということです。ですから安保法制に反対の人は、元最高裁判事、元長官まで反対している。憲法学者の99パーセントが反対している。元内閣法制局長官も反対している。しかしその反対のかなりの部分は、日米同盟を認めた上でのことです。つまりこれまでの戦後日本が良かったのだ、平和だったのだ、それを守らなければならない、こういう前提があるのです。
ではその平和の内実はと言えば、これは憲法と日米安保と自衛隊の三点セットなのです。安保体制はその内の一つ、三つが絡み合っている内の一つなのですけれども、これが朝鮮戦争の時、ベトナム戦争の時、あるいは湾岸戦争、イラク戦争の時にどういう役割を果たしたのか。日本にある米軍基地から米軍は出撃していっているわけです。果たして戦後日本は戦争に加担しなかったのか。そして沖縄の犠牲はそこでどうなっていたのか。こういうことを考えた時に、安保法制を阻止した上で、安保体制そのものを問わなければいけない。安保解消を目指す人は2パーセントしかいないのですが、これはいかに難しいかということなのですけれども、私はやはりそれをあきらめるべきではないと思います。
他者認識の欠落
徐 最近、若い真摯なアーティストで、日本の特攻隊の記憶を作品化している人と知り合いになりました。自分の作品と百田尚樹氏の「永遠のゼロ」とをいっしょにしないでほしいと言っています。もちろん、彼は百田氏のような差別主義者でも国家主義者でもありません。好感のもてる人物です。しかし、彼の作品からも私が感じることは、語りが内向きであり、そこに他者がいない、ということです。日本国家と兵士(その家族)しか、いない。けれども、特攻隊というのは特別攻撃隊ですから、あれは攻撃なのです。操縦士は死ぬことを運命づけられて「自らそれを受け入れている」のだけれど、実際には誰かを殺しに行っているのです。ぎりぎりに、最終的に圧倒的な戦力を持つ米軍に向けられた自殺攻撃なのだけれど、そういう攻撃にまで至った経過のなかでは、どれほど多数の他者を殺してきたのか。その部分を捨象して自己犠牲という物語だけが抜き出され、それを必ずしも右派的でない人たちも共有している、それが特攻隊の物語なのです。つまりそこには、他者が、相手がまったく欠落している。あれは攻撃なのだ。他者を攻撃した。よくなかった。あの戦争の結果、自分たちは他者を害した、敗戦後そういうところから出発することができなかった。福島も同じ、沖縄も同じ。それが、日本国民の守るべき戦後の平和だという言説には、やはり大きな欠落があるのです。一言でいうと他者認識の欠落です。
他者とじかに向い合って平和を構築する
他者が欠落しても、米軍のような、アメリカのような強大国の傘のもとで、いま高橋さんが言われていた自発的隷属によるかりそめの安定があるかもしれないけれども、他者とじかに向い合ってそこに平和を構築することはできません。他者認識が欠落しているのだから、国際政治に限っていっても、中国、韓国、北朝鮮等の人々と直接に対話して平和に結びつけることはできません。その次元に進めるかどうかということが、シールズをふくめていまの「安保法制」に反対している人たちに問われている点だと思っています。
それは難しい課題です。日本の思想としてみた場合に、そういう問いかけをどれぐらいの人がしただろうか、どれぐらいの人がそれをまじめに受け止めただろうか、そう考えると呆然とするぐらい難しい課題です。しかしいよいよその課題がほんとうに重要なものとして目の前に立ちはだかっていると私は思っています。
『奪われた野にも春は来るか 鄭周河写真展の記録』は福島原発事故以後のさまざまな問題を論じた本ですけれども、その事故以後4年半経過した現在、安保法制という大きな曲がり角に際して、そういう文脈のなかで読んでいただけたらとてもありがたいと思っています。
徐京植さん
一九五一年京都市生まれ。作家、東京経済大学教授。主な著書『私の西洋美術巡礼』『私の西洋音楽巡礼』『プリーモ・レーヴィへの旅』『ディアスポラ紀行―追放された者のまなざし』『植民地主義の暴力』『在日朝鮮人ってどんなひと?』『フクシマを歩いて』『越境画廊 私の朝鮮美術巡礼』他多数。
高橋哲哉さん
一九五六年福島県生まれ。哲学者、東京大学教授。著書に『逆光のロゴス』『記憶のエチカ』『戦後責任論』『歴史/修正主義』『証言のポリティクス』『反・哲学入門』『教育と国家』『国家と犠牲』『犠牲のシステム 福島・沖縄』『沖縄の米軍基地「県外移設」を考える』『いのちと責任―対談 高史明・高橋哲哉』など。
 ホーム
ホーム ご注文方法
ご注文方法 カートを見る
カートを見る お問い合わせ
お問い合わせ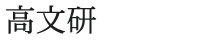
 関連書籍
関連書籍











