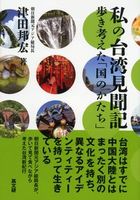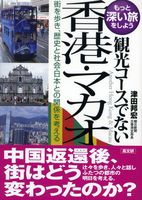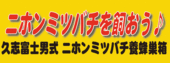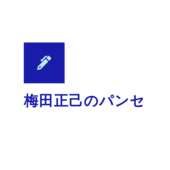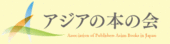- NEWS
アジア新風土記(105)ダライ・ラマ14世

|
著者紹介 津田 邦宏(つだ・くにひろ) 1946年東京生まれ。早稲田大学法学部卒業。72年、朝日新聞社入社。香港支局長、アジア総局長(バンコク)を務める。著書に『観光コースでない香港・マカオ』『私の台湾見聞記』『沖縄処分―台湾引揚者の悲哀』(以上、高文研)『香港返還』(杉山書店)などがある。 |
チベットのダライ・ラマ14世が2025年7月6日、90歳の誕生日を迎えた。インド北部のダラムサラではこの日、生誕を祝う祝賀会が開かれ、14世はチベット僧に支えられながら信者らの前に現れた。終始笑顔をみせ、「私には人としての使命がある。他の生きとし生けるものたちに奉仕するために生きている」と話した。「私自身は一人の仏教僧に過ぎない。人間的価値を高め、異なる宗教間の調和を促進する使命に取り組んでいく」とのメッセージも寄せた。
ダラムサラには14世と共にチベットを離れた人、その家族ら約1万人が暮らす。長寿を願う法要は寺院などで執り行われ、信者たちの祈りが広がっていった。
14世は1935年、ラサの北東約1千キロ、現在の青海省アムド地方の小さな村タクツェルで農業を営むチベット人家庭に生まれた。両親は広い谷間を見下ろす丘の上の小さな村で、大麦、そば、じゃがいもなどを育てていた。
「14世」になることについては「私自身なんの予感もなく、幼いときの記憶はごく普通である」と語り、「しいて思い出せば、子供たちが喧嘩するのを見るといつも弱そうな方についたという思い出があった」と回想する。(ダライ・ラマ法王14世日本公式サイト)
14世がラサのポタラ宮に入ったのは40年の冬、4歳のときだった。50年10月の中国軍のチベット侵攻から1か月後の11月17日、15歳にして正式にチベット社会の聖俗の指導者となる。
故郷のアムド地方はすでに中国軍に占拠され、僧侶の活動などが禁止されていた。51年の中国軍によるチベット併合後も、チベット人の抵抗は続いたが、59年の春になってついにインドへの脱出を決意する。(『アジア新風土記73』参照)
2025年7月2日、14世は後継者についての声明を発表、自身の死後、生まれ変わりが15世になるという「輪廻転生」制度の存続と、伝統に則っとった捜索とその転生を認定する権限はダライ・ラマ法王庁にあることを内外に明示した。声明はまた「他のいかなる者にもこの問題に干渉する権限はない」とした。
3月に出版された自伝には「新たなダライ・ラマは自由世界から生まれる」と書く。一般に転生とは現世でやり残した仕事をさらに続けて行うためのものといわれている。自身のやり残した仕事を継承する15世が中国の支配地域から生まれる可能性はないということか。
中国政府は「転生は中央政府の承認という原則を堅持しなければならない」と反発する。国務院・宗教事務条例(04年11月公布、17年6月改正)は「宗教指導者」の章を設け、36条に「チベット仏教の生きた仏陀の継承は、仏教団体の指導の下、宗教上の定められた方法に従い、省レベル以上の人民政府宗教部門または人民政府に報告され、承認を得る必要がある」と定める。
中国の見解は清朝時代のチベットとの関係に遡るともいわれる。
清朝は17世紀、チベットを異民族支配地の一つの藩部とした。ダライ・ラマについてはチベット人の精神的な支柱としてその存在を認める。チベットは朝貢国の一つになったが、従属の関係だったのか対等の関係だったのか。意見は分かれる。
清朝が20世紀初めの辛亥革命で崩壊すると、ダライ・ラマ13世は独立を宣言する。第2次大戦後、国共内戦に勝利した中国共産党は清朝時代の「チベット統治権」を継承すると主張、ダライ・ラマの転生についても中国政府が承認するとした。皇帝が絶対的な権力を持つ時代の制度と社会主義国の制度を繋ぐ論理とは何か。
14世の亡命生活は60年を超す。チベットの独立について言及することはなくなってきた。
武力による「チベット解放」が不可能な状況下にあっては、中国の一部であるということを容認しながら、チベット人の文化、宗教の独自性を認めてほしいという現実的な考えに立たざるを得ない。チベット側からすれば妥協とも受け取れる対応について、中国側は14世を分裂主義者と見做し、中国人とチベット人は一体であるという発想を捨てない。2012年の習近平指導部発足以来、同化政策は一層顕著になっている。
25年3月、ベトナム・ホーチミンで青海省ゴロク・チベット族自治州を中心にチベット語、文化の維持に積極的な役割を果たしていたチベット僧が不審死していたことが明らかになる。
7月7日の時事ウェブサイトは「トゥルク・フンカル・ドルジェ師(56)は中国政府が認定したパンチェン・ラマ11世の受け入れを拒否して取り調べを受け、ベトナムに逃れていた。3月25日、現地警察と中国の諜報員らに身柄を拘束され、3日後に死亡した」と報じる。
中国国内にドルジェ師のように同化政策に抗(あらが)う僧がどれだけいるのか、どのような扱いをうけているのか。実態はわからない。
チベットに王朝が興るのは5世紀ごろだ。
チベット自治区に青海、四川省の一部などを加えた広大なチベット高原は7世紀になるとソンツェン・ガンポが諸部族を統一して吐蕃王国を築く。インドから仏教も伝来、地域密教などを合わせたラマ教(チベット仏教)が生まれ、チベット文化が形成されていくことになる。独自の長い歴史と宗教、文化を培ってきたチベット民族を中華民族の一部とみなすことはできるのだろうか。
東京・上野の森美術館で09年9月に開かれた「聖地チベット ポタラ宮と天空の至宝」展を思い出す。主催者に中華文物交流協会、中国チベット文化保護発展協会が名を連ね、ダーキニー立像(仏教における精霊、女神)、金剛宝座如来坐像タンカ、仏塔、燭台など100を超す宝物が出品されていた。その一つ一つにチベットの風土を連想した以上に、美術館前に立って展示物が「中国の宝」とされたことに抗議する人たちの表情、眼差しに見た怒りに心が揺さぶられた記憶を思い起こした。
14世は90歳の誕生前日の長寿を願う法要で、「国を離れはしたが、心はいつもチベットとともにあると思っている」と話した。幼い14世が初めてラサに向かう途中、脳裏に刻まれたチベットの大地を14世の日本公式サイトが伝える。
「詳しいことはほとんど覚えていないが、道々出遭うものすべてがみな驚きであった。平原で草を食むドン(野生のヤク)の大群、点在するキャン(野生のロバ)の群れ、風のごとく軽やかに跳躍し疾駆するゴワ(チベットガゼル)やワ(小型のシカ)の幻のような姿。時々見かける、大声で鳴くガチョウの大群も楽しい眺めだった」
 ホーム
ホーム ご注文方法
ご注文方法 カートを見る
カートを見る お問い合わせ
お問い合わせ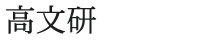
 関連書籍
関連書籍