- NEWS
アジア新風土記(73)チベット遠望

|
著者紹介 津田 邦宏(つだ・くにひろ) 1946年東京生まれ。早稲田大学法学部卒業。72年、朝日新聞社入社。香港支局長、アジア総局長(バンコク)を務める。著書に『観光コースでない香港・マカオ』『私の台湾見聞記』『沖縄処分―台湾引揚者の悲哀』(以上、高文研)『香港返還』(杉山書店)などがある。 |
いつの日かチベットを歩きたいと思う。
思いはしかし、なかなか叶えられそうにない。
インド亜大陸の広大な大地がヒマラヤの山々にぶつかり、その山裾に生まれたネパールにはチベットとインドを結ぶ古くからの交易路があった。
首都カトマンズから西に150キロほどの町ポカラからも隊商の道があった。
東にアンナプルナ、西にダウラギリの高峰の間を縫って流れるカリガンダキ川に沿った道は、いまでは自動車道が完成、ヒマラヤの奥懐までも容易に行けるようになった。
ダウラギリの高峰
ダウラギリの高峰
いくつもの峠越えの道をかつて歩いた時は、十数頭のラバの背に塩、雑貨などを積んだ隊商の一行と出会うことも度々だった。
暑い日差しが照りつける道を少しずつ登っていく。
一つの峠から尾根筋に差し掛かり、白い峰々への眺望が気分を和ませてくれる。
高度が上がっていくほどに辺りの木々が鬱蒼とした樹林になっていく。
雨季を前に空気はすでに十分湿気に満ちていた。
蒸し暑くほんの少しの山道でも汗が噴き出してくる。
濃い緑、薄い緑、様々の緑一色の世界に突然、パッと白く野生ランが咲いていた。
巨木の幹に細い枝をからませ、鮮やかだった。
オレンジ、赤の花も見つけ、まるで森の奥へ奥へと誘われているようだった。
道はさらに険しくなり、やがてあれほど豊かだった木も草も消え、暗灰色の乾いた礫、小石だけの大地に変わっていく。
渡渉するカリガンダキ川の水は冷たかった。
裸足の指一本一本に清冽な迸(ほとばし)りを残していく。
カリガンダキ川沿いの道にポーターたちは欠かせなかった
カリガンダキ川沿いの村の祭りに集まった人たち
山の中に時折、チベット仏教の寺院「ゴンパ」が見える。
寺から下りてきたのか臙脂(えんじ)色の僧服を着たラマ僧に出会う。
鉄砲傷を負った人たちもいた。
チベットはそのころすでに中国の「チベット自治区」になっていた。
ゴンパを拠点にチベットへのゲリラ活動を続ける人たちがいることはカトマンズで聞いていた。
目が合うと人懐っこい笑みが返ってきた。
ゲリラの兵士にはとても見えなかった。
ヒマラヤは丘の上に丘があり、山の上に山があった。
人々が行き来する道を外れ、小高い丘を登りきると緩やかな放牧地が広がっている。
村人たちのヤクが草を食んでいた。
小さな見張り小屋にはヨーグルトがつくられていた。
忘れられない味だった。
ヤクなどの放牧地
チベット族の少女
牧草地を突っ切りさらに丘の上へと登った。
地図を見比べながら5000メートルあたりまでは来たような気がした。
それほどの息切れもしなかったことを思えば、そこまで達していなかったのかもしれない。
青いケシ
村人しか通らない小道の小さな頂から北を望む。
山々の先には14世紀の中ごろに興ったチベット人のムスタン王国があった。
霞んだその遥か先はチベット高原だ。
「あるはずだ」と心に思いながら、しばし眺めていた。
ダウラギリ北方の山々
カリガンダキ川の道は明治時代の僧、河口慧海(かわぐちえかい)が仏典を求めて通った古道だ。
彼はダウラギリ北方の山々を越えてチベットに入る。
| 「南の方を眺めますとドーラギリーの高雪峰が雲際高く虚空に聳えて居る。高山雪路の長旅苦しい中にも遥かに北を眺めて見ると、チベット高原の山々が波を打ったごとくに見えて居るです(ママ)」(『チベット旅行記(上)』講談社学術文庫、2015年) |
慧海はチベット高原を8か月半かけて踏破、ラサ近郊に辿り着く。旅行記に
「山間の平原の中にズブリと立って居る山がある。その山の上に金色の光を放って居るのが日光に映じてきらきらと見えて居る」と書いたラサのポタラ宮は第2次大戦後、チベット族と中国軍との激しい戦いの時代を迎える。
中国は1951年、ラサに中国軍を進駐させ、チベット全土を併合する。
チベット族の遊牧地を取り上げ、大量の漢人を入植させていく政策に、チベット人の反発、抵抗は激しく、暴動、蜂起は相次いだ。
1959年3月10日、中国軍はダライ・ラマ14世を中国舞踊団観劇に招待、護衛らの同行を認めなかったことに不安を感じたラサ市民は数万人が集結、軍と衝突した。
14世は一兵卒に変装してポタラ宮を脱出、3週間かけてチベット東部からヒマラヤを越える。
ニューデリー北西部のダラムサラに亡命政府を樹立、3月10日は民族蜂起記念日となった。
中国政府は65年、チベットに自治区を設定、チベット独自の文化、言語を否定した中国化政策を進めた。
チベット人の抵抗は2008年の大規模デモとなって爆発する。
騒乱はラサから四川、青海、甘粛省へと広がった。
治安部隊の鎮圧後も14世の写真掲示の禁止などの宗教活動の封殺に焼身をもって抵抗した人たちは150人以上ともいわれる。
習近平国家主席は21年7月、国家主席として初めて自治区を訪問、「共産党中央のチベット政策は完全に正しい」と述べる。
ラマ僧にはチベット仏教が社会主義に適応するよう積極的な役割を求めた。
チベット人も中華民族の一員であるべきだというメッセージだった。
いま、チベットから聞こえてくるものに何があるだろうか。
自治区からの報道は限られている。
24年2月、四川省のチベット族居住地域でのダム建設に反対する住民が多数拘束されたと伝えられたが、動乱のときのような激しい衝突は過去のものとなったのか。
焼身自殺も22年3月にラサで起きたという情報があるが、それだけだろうか。
チベットは沈黙の時代に入ってしまったのか。
ネパールの山中で会ったラマ僧を思い出す。
笑みの奥に隠された信仰、抵抗のエネルギーを思う。
チベットの風土に築き上げられてきた民族の力を一体、消せるものなのか。
ダライ・ラマ14世がインドに亡命してから65年になる。
23歳だった14世も24年7月6日には89歳になる。
チベット仏教は「活仏」は生まれ変わりの少年が跡を継ぐ。
1989年、活仏の一人、パンチョン・ラマ10世が死去したとき、中国政府は14世が認めた後継者を廃して新たな11世を立てている。
14世は「恣意的な選定」を怖れ、民主的に15世を誕生させる考えを示す。
中国が認めることはないだろう。
チベットの人たちは二人の「ダライ・ラマ」が生まれたとき、その事実をどのように受け止めるのか。チベット社会はさらに分断されていくのだろうか。
 ホーム
ホーム ご注文方法
ご注文方法 カートを見る
カートを見る お問い合わせ
お問い合わせ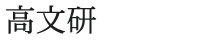
 関連書籍
関連書籍











