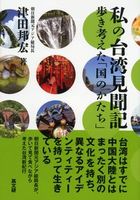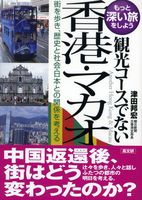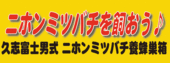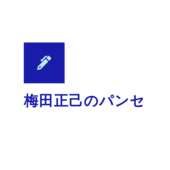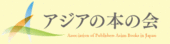- NEWS
アジア新風土記(110)阿里山

|
著者紹介 津田 邦宏(つだ・くにひろ) 1946年東京生まれ。早稲田大学法学部卒業。72年、朝日新聞社入社。香港支局長、アジア総局長(バンコク)を務める。著書に『観光コースでない香港・マカオ』『私の台湾見聞記』『沖縄処分―台湾引揚者の悲哀』(以上、高文研)『香港返還』(杉山書店)などがある。 |
台湾中央部のほぼ真ん中に位置する阿里山は最高峰玉山(旧新高山、標高3952m)の西北にその豊かな山容を見せる。
単独峰ではなく18の山々を総称して古くから阿里山と呼ばれ、最も高い大塔山は標高2663メートルだ。
阿里山の森を歩いた。季節は夏の終わりだった。大気はなお、強烈な日差しを受けてエネルギーを十分に保っていた。高度は2000メートルを超す。
遊歩道が整備され、散策は快適だった。冷気が汗ばんだ肌に優しい。
針葉樹の森はタイワンヒノキ(台湾檜)、ベニヒノキ(紅檜)を中心にツガ、モミなどが混在していた。思いの外明るかった。若木が多いからだろうか。
懐かしさに包まれていく山道だった。一人で歩いていると、台湾の森なのか、日本の森なのか、わからなくなる。時々行き交う観光客の中国語が辛うじて、台湾の森だということを思い起こさせてくれる。
阿里山の原生林
樹齢は千年を超えるか
伐採木の切株はすでに苔むしていた
樹齢千年を超すのではないかと思う巨木が所々にあった。老木と形容するには若々しく、枝葉を存分に広げていた。
幹に番号がついている巨木は伐採を免れた生き残りだ。
20本以上は残る樹齢千年から二千年前後のベニヒノキには番号がついていると聞いていた。大きな切株は切り倒された巨木の痕跡だった。
散策路は森の奥まで続いていた。次第に観光客も少なくなっていく。
辺りから人の気配が消えていくと、山の霊気が下りてくるような気持になってくる。老木と切株を眺めながら、人が足を踏み入れる前の時代を思った。
木々と大気の交わりだけが営々と続いていたころの山と森を想像した。
森の奥に「塔山」という処がある。
戦前の日本の森林経営に深く携わった河合鈰太郎は先住民の言葉で塔山は「化物山」を意味すると書く。
「阿里山の先住民は百三十三戸、老幼男女合わせ千五百人が暮らしている。彼等の考えでは魂というものは二つある。死ぬと一つは天に昇り、一つは化物山に行って住むと信じている。そのため、どこにでも猟に出かけるが、この山だけはよほどの不猟でもないと行かないという。塔山の奥は先住民でさえ道を知らないので入ることができない」(『臺灣協會會報第六拾四號』所収、明治37年1月)
「阿里山の先住民」はツォウ(鄒)族のことだ。
いまも阿里山郷に約6700人が暮らす。
先住の民にとって魂が宿る森には、18世紀の清朝・乾隆帝時代から漢人の入植が始まる。
1894(明治27)の日清戦争で勝利した日本は翌年の下関条約で台湾を領有、台湾総督府は直ちに山岳地帯の調査を開始、玉山の西に樹齢千年以上と推定される針葉樹の原生林が広がっていることを発見する。
総督府はドイツで近代林業を学んだ河合を招聘、本格的な林業開発に乗り出した。
1914(大正3)年、阿里山森林鉄道が阿里山・沼の平(現沼平)から山裾の嘉義の町まで72.7キロが完成する。
この鉄道によって搬出されたタイワンヒノキの大木は日本にも運ばれ、神社仏閣などの建築資材として活用された。ベニヒノキに比べ耐久性に優れているので最優良材として伐採されたという。ベニヒノキの巨木が残ったのは、こうした理由などによるという説もある。
森林鉄道わきのベニヒノキの倒木。樹齢三千年といわれ、戦後の2度の台風で倒れる
鉄道の車両は鮮やかだった
1920(大正9)年創建の明治神宮大鳥居も阿里山のタイワンヒノキだった。
『明治神宮造営誌』(内務省神社局、1930年)には
「用材は總数三十八本、材積尺締千三百八十四本、總て臺灣総督府の進献にして、其の最も長大なるものは長さ五十五尺、直径六尺六寸、樹齢一千二百八十四年に達し、嘉義驛を距る東方四十一哩、新高山の西腹より伐採せしと云ふ」
とある。大鳥居は1960年に老朽化、同じタイワンヒノキによって立て直された。現在は埼玉県の氷川神社鳥居に移築されている。
台湾のウエブサイト「台湾の伐採時代に何本の木が伐採されたか」(李根正、2016年)は『中華民国臺灣森林志』(姚鶴年著)によると、戦前の伐採面積9773ヘクタール、347万立法メートルの立木を伐採、207万立法メートルの木材を取得した」と伝える。この数字からどれほどの森が消えたかを推し量ることは難しい。『臺灣森林志』のデータを他の資料から確認することはできなかったが、戦前、戦後を通じて広大な森林が消滅したのは確かなことだろう。
針葉樹の伐採は戦後の国民政府(台湾政府)時代も継続され、91年になってようやく天然林の伐採が禁止された。
政府は2001年、森林鉄道の阿里山駅を中心とした1400ヘクタールを「阿里山国家森林遊楽区」に指定する。鉄道は戦前から旅客用としても活用され、1986年には玉山展望を目的とした祝山線ができる。
2009年と15年に台風の直撃を受けると一部線路が崩落、阿里山周辺の路線だけが運転を続けた。
祝山駅展望所から玉山を望む
祝山線終着駅の祝山駅は駅舎からの急な階段を登り切ると、目の前に玉山と左右に連なる山並みが一望だった。東の空がやがて曙色に染まっていき、日の出を迎える。一瞬の僥倖だった。雨がぱらつき出し雲海が流れる。煙雨はやがて驟雨となって山々を覆い隠した。
24年7月、森林鉄道は15年振りに全線が開通する。
15年の台風で崩壊した難所の「42号トンネル(標高約1500m)」は、近くに延長約1100メートルの新たなトンネルを建設することで乗り越えた。沿線に光ファイバーを施設して落石の監視システムを設置するなど安全性も強化した。
嘉義から阿里山までは旅客バスで2時間ほどで着く。鉄道の半分以下の所要時間だが、それでも鉄道の全線開通を心待ちにしていた人たちが多かった。バスにはない何かがあるのかもしれない。
阿里山駅
阿里山駅近くの食堂メニューに阿里山コーヒーを見つける。
産地で飲むことのできる数少ないコーヒーだ。標高2216メートルの地は空気が冷たかった。カップから立ち上がる香りとほのかな甘さに惹きつけられた。
注文した「阿里山」に山の上の味わいと風景を重ねる。山と森、風、雨に心が移ってしばし、時を忘れさせてくれた
ヒメヒオウギズイセン(射干菖蒲)
 ホーム
ホーム ご注文方法
ご注文方法 カートを見る
カートを見る お問い合わせ
お問い合わせ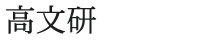
 関連書籍
関連書籍