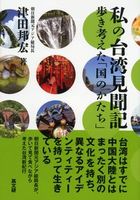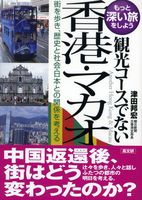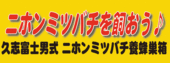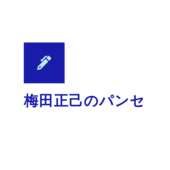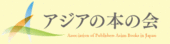- NEWS
アジア新風土記(108)チベットの巨大ダム

|
著者紹介 津田 邦宏(つだ・くにひろ) 1946年東京生まれ。早稲田大学法学部卒業。72年、朝日新聞社入社。香港支局長、アジア総局長(バンコク)を務める。著書に『観光コースでない香港・マカオ』『私の台湾見聞記』『沖縄処分―台湾引揚者の悲哀』(以上、高文研)『香港返還』(杉山書店)などがある。 |
バングラデシュ(バングラ)をサイクローンが襲った後、首都のダッカから南部のチッタゴンに向かう途中、ベンガル湾口に巨大なデルタをつくる大河の流れを眺めたことがある。
大河はガンジス川、ジョムナ川、メグナ川が合流して生まれた。
どこまでがガンジスで、どこまでがジョムナなのか。
見渡す限りの水面からは想像すらできない。
嵐が吹き荒れた後の流れに所々、流木を見つける。家屋の残骸もあった。
大河は僅かな痕跡を残して、微かな物音さえも押し殺すかのように静まり返っていた。その水量の豊かさに圧倒される。
水は豊かであるがゆえに広大なガンジスデルタをもたらし、詩人タゴールは「黄金のベンガル」とうたった。人々はそれが時に生死を分かつほどの凶暴さを孕んでいたとしてもなお、その恵みの中に生きてきた。(『アジア新風土記34』参照)
黄金のベンガルは三つの河川の一つ、ジョムナ川の源流であるチベット・ヤルツァンポ川(雅魯蔵布江)の巨大ダムによって失われていくのか。
ヤルツァンポ川はヒマラヤ山脈の北側からチベット高原南部を東進、東チベットのニンティ近くで大きく湾曲、「大屈曲部」といわれる深い渓谷を南下する。
インドに入るとブラマプトラ川と名を変え、アルナーチャル・プラデーシュ州からアッサム州を西に流れ、バングラではジョムナ川となってガンジス川などに合流する。全長2900キロの世界有数の「国際河川」だ。
2025年7月19日、国営新華社通信はニンティでヤルツァンポ川大屈曲部の「メトク(墨脱)ダム」の着工式が行われたと伝える。
同通信によると総建設費は約1兆2千億元(約25兆円)で、30年代の操業開始を見込む。ダムの他に5つの発電施設も建設される。
総発電量は年間3千億キロワット時で長江の三峡ダムの約3倍にあたる。
米ブルームバーグウエブサイトによると、大屈曲部は約50キロメートル続き、2000メートル以上も標高を下げて流れ落ちるという。(25年7月31日)
メトクダムは脱炭素電源の確保に加えて停滞する中国経済を再活性化させる狙いがある。大規模な建設事業によるインフラ整備、建築資材の需要、雇用創出などで景気を押し上げる政策は1993年に着工された三峡ダム建設時にも指摘されていた。
チベット経済を促進させるという側面もある。
習近平国家主席は8月21日、ラサで行われたチベット自治区成立60年を祝う式典に党最高指導部メンバーを率いて初めて参加、王滬寧・全国政治協商会議主席は「チベットは経済と社会の発展において歴史的な成果を収めた」と挨拶する。
中国は7月のダライ・ラマ14世の「輪廻転生」制度存続発言に、中国政府の承認が必要との立場を崩さない。チベットの発展と中国化は成し遂げなければならない命題になり、工事の本格化は多くの漢人労働者をチベットに呼び込むことで同化政策につながっていく。
インドはベンガル地方の豊かな土壌が損なわれ、農業、漁業などに携わる数百万人の生活に影響を与えると批判する。
ニューデリーのブラーマ・チェラニー政策研究センター教授は「季節ごとの沈泥(粒径が砂よりも細かく、粘土よりも粗い土、シルト)の供給がなければ、アッサム州およびバングラデシュは、肥沃な天然土壌を失うことになる」と語る。(「ニューズウィークウェブサイト日本版」25年7月26日)
大屈曲部の地盤への懸念もある。
1950年8月、ニンティの南250キロほどのアルナーチャル・ブラデーシュ州の山岳地帯を震源とするマグニチュード8・6のアッサム・チベット地震が発生、土砂ダムなどの決壊でアッサム、チベット両地方で約4800人の死者が出た。
インドプレート、ユーラシアプレートという二つの大陸プレートが衝突した地震では最大級といわれる。ダム建設予定地には活断層が走るとの言及もある。(陳ヨウ旭「国際河川の水資源に伴う中国とインドの紛争―ブラマプトラ川を事例として―」、明治大学学術成果リポジトリ、2022年)再び大地震が起こる可能性はないのか。
中国外交部はヤルツァンポ川のダム建設は中国の主権の範囲内だと強調、流域全体の防災上有益であり下流域国との協力を強化していくと説明するに留まる。具体的な内容にまで踏み込んだ発言は聞こえてこない。
水資源の確保という問題は領土紛争に発展する危険性も内包する。
アルナーチャル・ブラデーシュ州は1914年に英国とチベットが合意した国境線・マクマホンラインの南側に位置し、現在はインドが実効支配する。
中国は自国領の「蔵南地区」だとして譲らない。
同州でのダム建設計画も火種の一つになるかもしれない。
2019年にブラマプトラ川支流ディバン川の水力発電プロジェクトが承認されたが、少数民族の移住問題、環境への悪影響などを理由に反対運動が起きて頓挫している。
インドはメトクダム完成後に衝突などが起きた場合、ブラマプトラ川の流量が中国によって恣意的に操作されるのではないかと危惧する。
一方でディバン川のダム工事が始まった場合、「薩南地区」を主張する中国の抗議がどのようなものになるかの予測はつかない。
中国とインドはバングラ、ミャンマーを加えた4か国の地域協力フォーラム(BCIM)のメンバーだ。ただ、フォーラムは経済協力が主な目的だ。
国境紛争、水問題といったセンシティブな問題はテーマにはなりにくい。
インドとバングラの関係も24年7月のダッカでの反政府デモによってインドに脱出したハシナ元首相の引き渡しを巡って対立している。
両国が協力して中国に対抗する動きはない。
国際河川は上流部と下流部とでは常に利害がぶつかる。
東南アジアを流れるメコン川も中国のダムによるメコンデルタの水量低下が土壌の塩分濃度を高くしたり、タイで乾季の水位上昇による漁業への影響が出たりしている。中国側は影響を否定、論議は平行線をたどる。(『アジア新風土記62』参照)
水資源問題の難しさは、ダムの影響が直ちに現れないことだ。
デルタ地帯への水量変化などを見極めるには相当の年月を必要とする。
しかも一度完成したダム周辺部を元の状態に戻すことはほぼ不可能だ。
各国の環境変化への見解を検証、協議する場が生まれる状況は見えてこない。
 ホーム
ホーム ご注文方法
ご注文方法 カートを見る
カートを見る お問い合わせ
お問い合わせ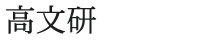
 関連書籍
関連書籍