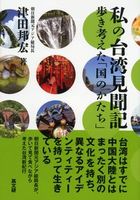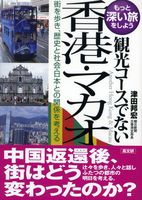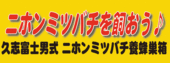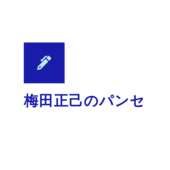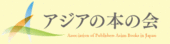- NEWS
アジア新風土記(107)戦場にかける橋

|
著者紹介 津田 邦宏(つだ・くにひろ) 1946年東京生まれ。早稲田大学法学部卒業。72年、朝日新聞社入社。香港支局長、アジア総局長(バンコク)を務める。著書に『観光コースでない香港・マカオ』『私の台湾見聞記』『沖縄処分―台湾引揚者の悲哀』(以上、高文研)『香港返還』(杉山書店)などがある。 |
東京・靖国神社の遊就館で「終戦八十年戦跡写真展」が2025年3月から12月まで開かれている。写真展の最初のコーナーには「大東亜戦争全般作戦図」という大きなパネルがあった。
終戦八十年戦跡写真展
日本を中心にした円形の地図は北東4000キロのアリューシャン列島、東6000キロのハワイ諸島、赤道を超えて6000キロ南のニューギニア、さらには西5000キロのインドまでが描かれている。
広大な地図を見ながら、これだけのエリアでそこに暮らす人たちを戦火に巻き込んだ日本、旧日本軍の痕跡の大きさと愚かさを改めて思い知る。
慰霊活動の概要も展示されていた
東部ニューギニア、ガタルカナル島、フィリピン、硫黄島などと題されたブースが続き、建立された慰霊碑、父親が戦死した場所で手を合わせる遺族、密林での遺骨捜索活動、旧日本軍の主力野砲、榴弾砲、鉄兜などの写真が展示されていた。
アリューシャン列島のブースにはアッツ島に夏に咲く藤色のルピナスと上陸した米軍の臨時滑走路用の鉄板が並ぶ一枚があった。
慰霊祭に使う花輪をつくる子供たちの写真は東部ニューギニアだった。
「インパール」は黄銅色の道路と両脇の叢、遠くに山並みが続く大きな写真が目に留まる。畔で方形に仕切られた水田も写っていた。
写真家、杉山正己氏が2017(平成29)年に撮影した。ゆったりとしたのどかとも言える自然を切り取った一枚はおよそ戦争という言葉とは無縁の世界に思えた。
パンフレットの説明には日本軍将兵の行軍、撤退について「夜間、密林、尾根歩きが多く、こうした広大なインパールの風景をゆっくり目に出来なかったであろう」とあった。
インパールの風景
インパールはインド北東部、アッサム地方の要衝の地だ。
1942年5月までに英領ビルマ(ミャンマー)のほぼ全域を占領した旧日本軍は44年3月、急峻な山岳地帯と熱帯雨林の中を400キロ行軍するというインパール作戦を展開する。
しかし、雨季に入って渡渉する川の水嵩は増加、マラリアなどに苦しめられる。補給物資も届かず、7月には作戦中止の命令が下る。撤退は進軍に増して悲惨を極め、7万5千人の死傷者を出したと言われる。
インパール作戦の直前にはタイから英領ビルマへの補給路確保のための泰緬鉄道415キロが完成する。工事には連合国軍捕虜6万5千人、東南アジア各地から徴用した現地労働者ら約40万人がかかわったといわれる。
当時の状況の一端は54年の英映画「戦場にかける橋」によって窺い知ることができる。
タイ側の拠点の一つであるカンチャナブリの町はバンコクから西北に約125キロのところにある。
町の一角を流れる通称クワイ河にかかる橋が「戦場にかける橋」としてこの地を有名にした。
映画に登場した橋のモデルはミャンマー国境に近いソンカリア川にかかるソンクライ橋ともいわれている。
25年ほど前の「戦場にかける橋」。いまも変わらないのではないか
戦場にかける橋
「戦場にかける橋」は背丈の低い鉄骨が剝き出しのシンプルな鉄橋だった。
すっかり整備された橋からは往時の様子を偲ばせるものはなにもなかった。
過酷な労働に思いを馳せるにはよほどの想像力を必要とした。
河の流れはゆるやかだった。風が吹くとわずかに川面が揺れた。
日が傾くほどに辺りの景色は一層深く沈んでいった。
クワイ河の流れは静かだった
英連邦戦死者墓地
カンチャナブリの一角に英連邦の戦争墓地があった。
平らな方形の墓碑が整然と並び、墓碑と墓碑の間にはバラなどが植えられていた。鉄道工事で命を落とした捕虜らの墓だった。
日本の敗戦後、連合国軍は線路沿いに捕虜たちの墓地を3週間かけて捜索した。
元カンチャナブリ憲兵分隊の永瀬隆氏が通訳として加わったことを、同行記『虎と十字架』(『ドキュメントクワイ河捕虜墓地捜索行』所収、社会思想社・現代教養文庫、1988年)で知る。
捜索隊は旧日本兵に灌木を切らせ、雑草を払わせ、パパイヤの木を押しのけての作業だった。草いきれのたちこめる中での捜索だった。見つけた墓を示す十字架は土か木片かと見紛うものだった。「その下の地面が、ちょうどひとり寝られる大きさで矩形に地面が凹んでいた。人を埋めたあと地面に盛り上げた土が、歳月の重さで締まって陥没したものだ」
永瀬氏はその後もタイに100回以上も訪れ、慰霊の旅を続けた。
クワイ河平和基金を立ち上げ、日本への留学生支援などにも取り組んだ。
「沿線に沿ってすべての悲劇を目撃したのは私しかいない。とにかく、ジャングルの中で受けたあの激しい衝撃、あれが私の人生を変えてしまいましたね」(『クワイ河に虹をかけた男』満田康弘、梨の木舎、2011年)
横浜市保土ヶ谷区にある英連邦戦死者墓地では1995年から毎年の夏、日本で亡くなった捕虜らを追悼する礼拝が続いている。
永瀬氏がオーストラリアで日本軍捕虜が手厚く葬られていることを目の当たりにして、呼びかけたのが始まりだった。
2025年8月2日、31回目の英連邦戦没捕虜追悼礼拝はお年寄りから高校生まで約150人が参加した。英国、カナダなどの駐在武官らも参列した。
墓地は英国軍、オーストラリア軍などの捕虜ら1873人が眠る。
墓碑と墓碑の間にはバラ、ラベンダーなどが植えられていた。
その風景はかつて見たカンチャナブリの墓地と変わらなかった。
「今年はいつもよりバラの咲き具合が遅い」と一人が話していた。
日差しは強く墓地を取り囲む木々からの風もときに熱風のように感じられた。
日本聖公会東京教区・大森明彦司祭の追悼の辞に「この礼拝が最も暑い季節の11時に行われるのは、捕虜の方たちが炎天下で立たされた痛みを追体験するためです」という言葉があった。
参列者らの献花が続いた
少し小高い一隅にインド兵らの墓碑が並んでいた。
太平洋戦争中のインドは英領インドだった。
日本の地でどのような思いで逝ったのか。
英連邦軍の一員としての誇りはあったのだろうか。
墓地に植民地のにおいはなかった。そのことが微かなわだかまりを残した。
インド人捕虜らの墓碑が並んでいた
わだかまりは日本の戦後への思いに結びついていく。
日本もまた植民地を放棄したことでその記憶を希薄にさせた。
連合国軍の占領によって生まれた「平和な時代」に、台湾では1947年の2・28事件で国民政府軍によって2万人以上の人たちが殺害され行方不明となった。
1年後には韓国・済州島で4・3事件が起きた。
旧植民地での惨状は知らない土地、人々の話として伝えられてこなかったか。
1945年から1年が過ぎ、また1年が過ぎていく。日本が植民地を持ったという事実はどこまで人々の心に共有されているのだろうか。
 ホーム
ホーム ご注文方法
ご注文方法 カートを見る
カートを見る お問い合わせ
お問い合わせ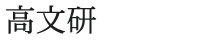
 関連書籍
関連書籍