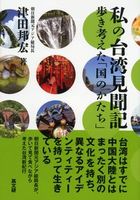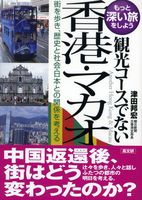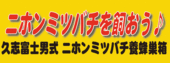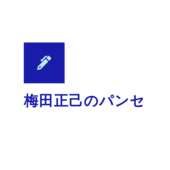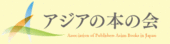- NEWS
アジア新風土記(106)台湾・立法委員のリコール不成立

|
著者紹介 津田 邦宏(つだ・くにひろ) 1946年東京生まれ。早稲田大学法学部卒業。72年、朝日新聞社入社。香港支局長、アジア総局長(バンコク)を務める。著書に『観光コースでない香港・マカオ』『私の台湾見聞記』『沖縄処分―台湾引揚者の悲哀』(以上、高文研)『香港返還』(杉山書店)などがある。 |
2025年7月26日、台湾の国民党立法委員(国会議員)24人のリコール(解職請求)についてその賛否を問う投票が一斉に行われ、いずれも反対票が賛成票を上回り、リコールは不成立に終わった。立法委員に対するリコール投票は21年10月に民進党系委員に対して初めて実施されたが、今回は過去に前例のない大規模なものだった。
リコール運動は24年1月の立法院(国会、定数113)選挙で少数与党に転落した民進党の第1党返り咲きを目論んだ支持団体などによって25年初めから全島で本格的に展開された。頼清徳総統は6月の民進党大会で運動の支持を表明していただけに求心力の低下は避けられない。8月23日にはさらに国民党立法委員7人のリコール投票もあるが、成立の見通しは立たず、政局運営は以前にも増して厳しくなりそうだ。
24年立法院選挙は野党・国民党が52議席を獲得して第1党となり、民進党は過半数に届かない51議席だった。(『アジア新風土記69』参照)
5月に就任した頼総統は議会運営の要である議長を国民党に明け渡し、同党主導の立法院職権行使法の改正によって総統の年1回の国情報告と報告に対する質問への回答を義務づけられるなど、フリーハンドの政策遂行が大幅に制限された。
25年予算は政府案の6.6%にあたる2075億台湾ドルが減額され、地方自治体への一般補助金も25%カットされた。「抗中保台(中国に対抗して台湾を守る)」を掲げる政権にとって重要な国防費も大幅な譲歩を迫られる。
当初案の6470億台湾ドルから軍事装備関連費の3%削減に加えて潜水艦開発費の5割にあたる10億台湾ドルも凍結されるなど、国防計画に大きな齟齬をきたすのではと指摘された。
第3党の民衆党(8議席)が国民党と共に与党批判に終始したことも、苦しい議会運営に拍車をかけた。少数与党といういわば片肺飛行を余儀なくされた政権は韓国と同じだったが、与野党の差が大き過ぎた韓国と違って、勢力が拮抗していたからこそリコールの動きが出てきたともいえる。
台湾の人たちには立法院選挙から1年しか経っていないとき、有権者の審判を半ば無視する形の解職要求を早計に過ぎるとみる気持ちがあった。蔡英文前総統時代から長く続く民進党政権の傲慢な手法ととらえる人も少なくなかった。
リコール対象の国民党委員が中国に融和的だという批判は対立を煽って社会を分断させかねないとの危機感を生む。頼総統の中国に対して団結して台湾を守ろうという訴えも、野党勢力を「不純物」とみなすような発言などが反発を招いた。
運動への懐疑的な空気がもたらしたとも言える投票結果は、台湾が成熟した社会だということの一つの証になったのではないか。
立法院の与野党逆転というシナリオはほぼ消えた。頼総統の基本姿勢への影響はどうか。就任1年目の談話では「私たちはアジアの民主主義の灯台だ」と述べて台湾の重要性を強調した。中国には「境外敵対勢力」との認識を表明している。そのスタンスに変わりはないとみられる。ただ、政権が頼りとする米国の安保政策は従来通りの曖昧さを残したままだ。人々の暮らしに直結する経済もトランプ政権との関税問題などは先行き不透明であり、景気の安定が揺らぎかねない脆さを内包する。変調をきたせば大陸との積極的な経済活動を求める意見が強くなることにもなる。
国民党もリコール不成立に向けた支持者の掘り起こしがそれなりに実ったとはいえ、もともと優勢な選挙区であり諸手を挙げて喜ぶほどの状況にはない。民進党に対抗して民進党立法委員15人のリコールを試みたが、賛否投票の前提となる選挙区有権者総数の10パーセント以上の署名を集めることができず、支持層の薄さを改めて露呈した。リコール阻止を「勝利」と考えてこれまでと同様な議会運営を続けていけば、有権者は離反していく。中国とより密接な関係を築くべきだとの一貫した主張も大陸との距離に明確な方向性は見出せていない。過去の総統選挙は台湾人としてのアイデンティティを持つ人たちの十分な支持は得られず、3期連続して敗退している。中国が民進党の退潮ととらえ、国民党を通じて台湾統一にむけて圧力を強めることは予想される。どこまで「台湾の政党」としての主体性を保っていけるか。
民衆党はリコール運動をどのようにみているのだろうか。柯文哲主席のカリスマ的な人気と民進、国民両党に飽き足らない若者らを中心に支持を広げたものの、主席が収賄罪で起訴されて辞任、一気に勢いを失った。第3勢力として台湾政治のキャスティングボートを握り、両党と一線を画していれば、と思う。国民党の議会運営に一定の歯止めをかけていれば、リコール運動に弾みがつくこともなかったかもしれない。
立法院選投票前日の24年1月12日夜、台北の凱達格蘭大道(ケタガラン、総統府前大通り)で開かれた総決起大会には主催者発表で35万人が集まった。
熱気は数日前の同じ場所での民進、国民両党の決起大会をはるかに上回っていた。駆けつけた人々の歓声、拍手には現状への不満、怒りがあった。社会を変えたいという声はいま、行き場を失っている。
黄国昌・新主席は14年のひまわり学生運動をリードした経験を持つ。議会に是々非々の態度で臨み、若者らの期待に応える形で不安定な就労機会、賃金の伸び悩みなどに独自の政策を打ち出せれば、そこに再生への道筋が見えてくる。民進、国民の二大政党による硬直した政治状況を打ち破ることは社会の活性化に繋がっていく。
「真夏の選挙戦」は賛成、反対両派の集会を過熱させながら少なくとも2回目のリコール投票まで続く。与野党、支持者らの対立は激しくなっていくだろう。リコール運動は起死回生の策だったのか、あるいは禍根を残しかねない奇策だったのか。そのことを見極める難しさを考える。
立法院は今後の選挙でも与野党伯仲は起こり得る。同じような動きが生じる可能性もまた否定できない。民主制度に許された手続きとはいえ、選挙とリコールの繰り返しが常態化していく社会は、台湾の人たちの伸びやかで多様性に富んだ社会の在り様だろうか。台湾は「国政」の場に予測不能な手立てを持ち込んでしまったという思いは深い。
 ホーム
ホーム ご注文方法
ご注文方法 カートを見る
カートを見る お問い合わせ
お問い合わせ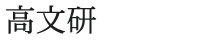
 関連書籍
関連書籍