- NEWS
アジア新風土記(63)モルディブ

|
著者紹介 津田 邦宏(つだ・くにひろ) 1946年東京生まれ。早稲田大学法学部卒業。72年、朝日新聞社入社。香港支局長、アジア総局長(バンコク)を務める。著書に『観光コースでない香港・マカオ』『私の台湾見聞記』『沖縄処分―台湾引揚者の悲哀』(以上、高文研)『香港返還』(杉山書店)などがある。 |
14世紀のモロッコの旅行家イブン・バットゥータがインド西海岸のカリカットから約940キロ南西のモルディブ群島に渡ったことはあまり知られていない。デリーのイスラム王朝トゥグルク朝に8年間滞在した彼はその後、北京を目指す途中の1343年から44年にかけて8か月ほど立ち寄る。東方に向かうルートを変えた理由は不明だ。
インド洋に広がるモルディブ群島は南北に約850キロも続くサンゴ礁の島々だ。旅行記『諸都市の新奇さと旅の驚異に関する観察者たちへの贈り物』は、モルディブのへの旅をこう書き出す。
| 「カーリクート(カリカット=筆者注)で船に乗り、海に出てから一〇日後、われわれはズィーバ・アルマハルの群島(モルディブ群島=同注)に着いた。(中略)この群島は、世界の数ある不思議の一つで、約二〇〇〇の島々、そのなかの一〇〇に近いもの(環礁)がそれぞれ輪型の飾りのように、円く集まっている」(『大旅行記6(東洋文庫691)』イブン・バットゥータ、イブン・ジュザイイ編、家島彦一訳注、平凡社、2001年) |
旅行記は島々の様子を伝える。
環礁には入口があり、船はそこからしか中に入れず、船が航路を誤ると風によってインド南東部、スリランカまで運ばれてしまう。
女性スルタンが統治する国の人々は敬虔なイスラム信徒だ。樹木の大半はココヤシで、わずかにモロコシの一種が採れるが、ほとんどの食料はマグロなどの魚介類だ。
ウラマー(イスラム法学者、指導者)でもあるイブン・バットゥータは政府高官の娘と結婚、法官としてイスラム法順守の日々を送ったが、政争に巻き込まれて群島を離れる。
モルディブはその後、ヨーロッパ列強の支配が続き、ポルトガルの占拠、オランダ保護領時代を経て1887年に英国の保護領となる。独立は戦後の1965年だ。英保護領時代からインドとの関係は深く、混乱が起きた時などはインド軍が派遣された。
南アジアの「一地域」でしかなかったモルディブは、中国の一帯一路政策によって国際社会の注目を集める。2013年のモルディブ大統領選に勝利したヤミーン氏は習近平国家主席を招いて同政策への支持を表明、従来のインドとの友好関係に距離を置いた。17年には中国と自由貿易協定(FTA)も締結する。しかし、多額の資金援助による空港、港などインフラ整備が中国依存を強めるなどとの批判を浴び、18年の大統領選に敗れる。
2023年9月9日に行われた大統領選は立候補者8人がいずれも過半数を得ることができず、30日の決選投票で親中国派のムハンマド・ムイズ候補(45)が54パーセントの支持を獲得、親インド路線の継続を訴えた現職のイブラヒム・ソリ候補(61)を破った。有権者約28万2千人の8割以上が投票した。大統領就任は11月の中旬が予定されている。
ムイズ氏は10月2日、首都のマレで「法に基づきインド軍部隊を撤収させる」と演説、モルディブ駐留インド軍の撤退を求める考えを明らかにする。インドは情報収集機4機を贈与、その運用のための治安部隊を派遣している。同氏は「モルディブ第一」を強調したものの、当選直後には資金洗浄の罪で禁固刑を受けていたヤミーン氏を自宅軟禁に切り替え、親密さをうかがわせた。親中政権の復活に中印両国とも表立った動きを見せていないが、新たな緊張の要因が一つ増えたことは確かだ。
最近の中印関係は良好とは言い難い状況が続く。中国が23年8月に公表した「標準地図」は、国境線を巡って対立するインド北東部のアルナチャルプラデシュ州と北西部のアクサイチン高原を中国領と明記する。インド外務省は「根拠のない主張を拒否する」との声明を発表したものの、野党国民会議派のガンディー元総裁がアクサイチン高原に隣接するラダック地方も「中国に侵略されている」と公言、対立色を強める。モディ首相としても24年春に予定されている総選挙を前に「弱腰」の対中政策はとれない。
モルディブ経済はヤミーン大統領時代の5年間、中国から多額の経済援助によって大幅に発展したともいわれ、18年8月のマレと空港のあるフルレ島を結ぶ海上橋の完成など交通インフラも整備された。援助の全体像は明らかになっていないが、国家債務、国家債務保証などを合わせて15億ドルほどにはなるとみられる。国民総生産(GDP)が60億ドル前後の国家にとっては決して少なくない額だ。債務返済をめぐってソリ政権がインドとの関係再構築による解決策を模索していたが、今後はどうなるのか。
中国はモルディブの「債務」が続く限り、海上交通路の要衝であるモルディブへの影響力を維持することになる。スリランカと同じような「債務の罠」に陥る可能性はあるのか。スリランカは南部ハンバントタ港の99年間の運営権を中国国営企業に手渡したが、モルディブには大型船が停泊できるような良港に恵まれていない。「良港建設」は中国が南シナ海の島々に港、空港を建設した例から見てもあり得ない話ではない。ただ、「内海」としている南シナ海とは状況が大きく異なる。インドとの無用なトラブルは避けたいはずだ。
イブン・バットゥータがモルディブを訪れてから70年後1413年、中国・明朝永楽帝の命を受けた鄭和(ていわ)が4度目の大航海の途に就いた。3回までの帆走ではインド・カリカットに入港している。新たな目的はさらに西の中東、アフリカ東海岸との交易の拡大だった。『鄭和』(寺田隆信、清水書院、1981年)によると、この航海で鄭和の分遣船隊は「溜山国(モルディブ)」に入り、中国への使節団派遣を招請している。通訳として同行したイスラム教徒の馬歓は風俗は純朴で美しく、女性は顔を覆い、特産物に龍涎香(りゅうぜんこう―マッコウクジラの腸内にできた結石)があるなどと紹介している。
イブン・バットゥータはモルディブの指導権争いのとき、インドの地方王朝に支援を求めたが果たされず、失意のうちに去ったといわれる。鄭和の分遣隊は北京までの遠路をどう説得したのか、馬歓のムスリム同胞への訴えはあったのか。そのような歴史の一つ一つを追っていくと、現代の政争がイブン・バットゥータに、中国の海洋進出が鄭和の大船隊にオーバーラップしてくる。「インド洋の真珠のネックレス」とも例えられ、南海の楽園のイメージが常に先行するモルディブの風土が生き生きとして精彩を放ち、陰影に富む歴史が脳裏に刻み込まれていく。その面白さに驚き、惹かれていく。
 ホーム
ホーム ご注文方法
ご注文方法 カートを見る
カートを見る お問い合わせ
お問い合わせ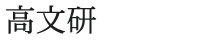
 関連書籍
関連書籍











