- NEWS
アジア新風土記(55)台湾・澎湖諸島

|
著者紹介 津田 邦宏(つだ・くにひろ) 1946年東京生まれ。早稲田大学法学部卒業。72年、朝日新聞社入社。香港支局長、アジア総局長(バンコク)を務める。著書に『観光コースでない香港・マカオ』『私の台湾見聞記』『沖縄処分―台湾引揚者の悲哀』(以上、高文研)『香港返還』(杉山書店)などがある。 |
台湾海峡の真ん中に「風之郷」と呼ばれる澎湖諸島がある。
台湾本島西海岸から約50キロ、中国大陸から約140キロ離れた大小90の島々は海抜100メートルを超す山や丘はなく、常に夏の台風、冬の季節風に晒されている。
特に北東から連日吹きつける寒風の「鹹雨(かんう)」は塩分を含んで樹木の生育を妨げ、殺風景な風景を演じさせる。
澎湖島の海辺には立ち枯れた木があった
島の女性たちは冬の強風から肌を守るために目の部分だけを残して頭から顔まですっぽりと布、タオルで覆っていた。
「封面巾」ともいわれる代々受け継がれてきた生活の知恵は、若い人ほど肌を隠すと聞いた。
訪れた20年以上も前には通りでも市場でも封面巾姿をよく見かけたが、いまはどうなのだろうか。
畑は隆起サンゴ、玄武岩を積み上げた高さ1~2メートルの防風壁「菜宅」で囲まれていた。
秋の浅い頃だったので鹹雨の凄さは実感できなかったが、菜宅の中でサツマイモを植えていた女性は「冬の風はいつも15メートルくらい。目なんかとても開けていられない」と話してくれたことがあった。
澎湖島・馬公の市場で落花生を売る封面巾姿の女性
菜宅で強風を防ぐ畑
大陸からの移住は唐代末の9世紀ごろから始まったとされ、1281年、元皇帝フビライは主島・澎湖島の媽宮(現在の馬公市)に警備と海賊取り締まりの澎湖巡検司を設置、大陸王朝の統治下にあることを明確にする。
島々は日本の倭寇が大陸沿岸から澎湖諸島を蹂躙する明代を経て17世紀に入ると、ポルトガル、オランダなどが進出する時代を迎える。
ポルトガルは澎湖諸島に「ペスカドーリス(漁師たち)」という名前をつけるが、「イラ・フォルモサ(麗しの島)」の台湾本島と同じく、その足跡をほとんど残していない。
すでに大陸にマカオという居留地を確保しており、その他の土地は眼中になかったということか。オランダは1622年6月22日から3日間にわたってマカオを攻撃したが敗退、7月11日に澎湖諸島に転進、媽宮に要塞を構える。
明朝はオランダに澎湖諸島放棄の代わりに台湾上陸を認めるという停戦案を提案する。オランダ東インド会社の業務日誌をまとめた『バタヴィア城日誌1』(村上直次郎訳注、東洋文庫170、平凡社、1970年)に、中国沿岸艦隊司令官ソングによる中国沿岸の出来事の報告(1625年4月9日)をみる。
「彼等は多数のジャンク船(木造帆船=筆者注)および兵士を率い、戦争の準備を整えて、自ら澎湖諸島に来たり、我等もし任意に澎湖島を去らずば、武力に訴えて去らしめんと欲し」
「主将ソウヤは(中略)我等を澎湖島より退去せしむるほかに任務を有せず、と答えたり」
「主将はまた我が国人が城を破壊して澎湖島を退去したる時は、貿易開始に対する福州の軍門の批准を我等のために得ることを約束せり」
「よって一六二四年八月二十六日、澎湖島の設備一切を破壊してタイワオン(現台南=筆者注)に向け退去せり」
オランダはタイオワンの要塞化に着手、入江に沿った小さな半島の先端にゼーランディア(熱蘭遮)城を築く。
当時の絵地図には城壁直下まで海が迫っている様子が描かれている。
翌年には商館を内陸部に移し、プロビンシャ城(赤崁楼)を構えた。
ゼーランディア城(史跡案内図より)
『バタヴィア城日誌』は明朝がこのような申し出をした理由については触れていない。
澎湖諸島が大陸に近く、漢人らが定住して媽祖廟を建立、廟を中心として街がつくられていたこと、澎湖より遠い台湾は占拠されても脅威は少ないことなどが考えられるが、それにしてもと思う。
日誌は中国の官人の話として、澎湖は雨期に始まる不健康な時期があり、派遣された者は1年以内に半ば死ぬ土地にオランダ人が留まるのは不思議だと伝える。
そのような土地に固執し、見返りに台湾を差し出す意図は何だったのか。
明朝はその時代すでに台湾を領土とは見なしていなかったということか。
台湾にはしかし、福建省などからの漢人が移り住んでいた。
明朝は冊封した友好国以外との交易を禁止しており、当時のタイオワンは
「日本人が毎年ジャンク船二、三艘にて渡来し、貿易を行なう所なり。(中略)中国より毎年、三、四艘のジャンク船、絹織物を積み来たりて日本人と取引せり」(『バタヴィア城日誌1』)という状況だった。
台湾総督府の西澤義徴税関長の「臺灣貿易史上の一挿話」(『臺灣時報』5期、1930年)は、タイオワンに居住する漢人は2万5000人を数え、その首領はほとんど海賊の頭目だったと書く。
西澤は出典を明らかにしておらず、日誌にも具体的な数を見つけることはできなかったものの、相当数の中国人が出入りしていたことは確かなのではないか。
「海賊」は澎湖諸島の人たちのような皇帝の民ではなかったのか。
日本が明治初めに「台湾出兵」したときの口実は、中国側から台湾には統治の及ばない先住民が暮らしているという言質をとったことだった。
歴代王朝の感覚は台湾の漢人もまた大陸とは異なる「化外の民」であり、その土地もまた「化外の地」だったのかもしれない。
台湾の漢人の多くは男たちだった。女たちが移り住むことはなかった。
そこも一家挙げて居を構えた澎湖とは異なっていた。
清代になっても台湾派遣の役人は単身が原則で妻らの同伴は許されず、「有唐山公、無唐山媽(大陸から来た祖父はいても、大陸からの祖母はいない」という言葉が生まれるほどだった。
男たちが先住民の女たちを娶ったことは、いまの台湾人の穏やかな性格形成に少なからぬ影響を与えているのではとも思う。
大陸の中国人男女が大挙して来るのは戦後の国共内戦に敗れた蒋介石の国民政府が台湾に逃れた後だ。
澎湖諸島はいま、中国と台湾の台湾海峡上の境界である「中間線」に近いことで「台湾有事」の際の拠点として注目されつつある。
台湾政府は約8000人の将兵を常駐させ、海峡全域がほとんど視界に入る強力レーダーを配備、対艦、対空のミサイル防衛システムもつくりあげている。海岸線には戦車のスムーズな走行を可能にさせる道路が整備され、毎月のように実弾演習が行われている。
蔡英文総統はじめ政府要人らの訪問も度々だ。
澎湖諸島はオランダの占拠と撤退の一時期を除いて、歴史の表舞台に登場することはなかった。
この400年間、「風之郷」は烈風との闘いだけに明け暮れたといってもよかった。現代史に「澎湖諸島」の名前が改めて刻まれことのないよう願わずにはいられない。
 ホーム
ホーム ご注文方法
ご注文方法 カートを見る
カートを見る お問い合わせ
お問い合わせ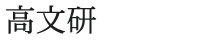
 関連書籍
関連書籍











