- NEWS
アジア新風土記(46)香港の「新年」

|
著者紹介 津田 邦宏(つだ・くにひろ) 1946年東京生まれ。早稲田大学法学部卒業。72年、朝日新聞社入社。香港支局長、アジア総局長(バンコク)を務める。著書に『観光コースでない香港・マカオ』『私の台湾見聞記』『沖縄処分―台湾引揚者の悲哀』(以上、高文研)『香港返還』(杉山書店)などがある。 |
新しい年への思いは旧暦で「新年」を迎えるアジアの人たちには一際(ひときわ)強いように感じる。旧暦の正月は春の訪れが間近にあり、季節の移ろいに人々の心が深く結びついているからだろうか。
2023年の旧正月(春節)は1月22日が元日(初一)だった。
香港の春はビルが林立する都市部ではなく、九龍半島の郊外や広東省・深圳と接する新界地区の田舎から訪れる。
手入れされた園芸農家の畑などから桃の香りが漂ってきて、人々は春の近いことを知る。
桃の木は咲き具合に一年の運勢をみるだけに、年末の「年宵花市」には欠かせない。
作家の邱永漢も香港にいた時は遠出して探した。「水揚げをよくするために、家内などは脱脂綿に水を含ませて木のまたにはさみ、一日に何度も水を替えてやる。そのかいあってか、わが家の桃は毎年みごとに咲く・・」(『食は広州に在り』中公文庫、1975年)
香港・新界地区の園芸農家。返還前後には大陸産の「桃の木」に押されていたが・・・
元日の朝、各家々の正月は花市などで慎重に選んだ桃の木とともに明ける。
年始めの膳には「年糕(ニンゴウ)」「蘿蔔糕(ローバッゴウ)」が顔を揃える。
年糕は甘めの餅、蘿蔔糕は大根餅で「糕」の発音が「高」と似ていることから、よりよい年になってほしいという気持ちに通じた。
元日は必ず精進料理を食べなければいけないとも言われ、香港人の食欲を満たす日は「開年(ホイニン)」という正月二日目(初二)だ。
街中のレストランが、干し牡蠣と海藻の入った豚の舌の煮込、子豚のローストなど、幸運を呼び込む特別メニューをつくって年始回りの客らを呼び込む。
各寺院もまた初詣客らで賑わう。九龍地区の道教寺院、黄大仙は「あらゆる願いをかなえる場所」として参拝客を集める。
長い線香を立ててお祈りをした後は占いだ。
占いの店が並ぶ路地は人で溢れ、お目当ての店に行き着くのも大変になる。
「年宵花市」。「金桔(キンカン)」の金は「財」、桔は「吉」を意味して縁起がいい。
花市の水仙。いい香りが福を呼び込むともいわれている。
花市には香港では普段見かけることの少ない「生花」が主役だ
新界地区沙田の車公廟は南宋の車公将軍の霊を祀る寺院だ。
地元の人らが幸運をもたらす彩り風車を求めて引きも切らない。
ビクトリア港で打ち上げられてきた恒例の花火はコロナ禍の影響で中止になったが、「初三」には沙田競馬場で正月競馬が開催され、多くの人が運だめしの馬券を握りしめた。
旧正月の日々を、かつて暮らしていたころを振り返りながら書いていくとき、正月行事はどれだけ受け継がれているのかと思う。
2023年の「新年」に香港の人たちは何を思い、何に希望を見出すのだろうか。
「一国二制度」が多くの人々の思い描いた社会とは別の制度になったいま、昔からの行事に心を預ける気持ちは生まれてくるのだろうか。
2022年の年末、香港映画を続けて3本見た。
『七人楽隊』は7人の監督が戦後から近未来までの香港をそれぞれの思いで切り取ったオムニバス映画だ。
1950年代のビルの屋上で少年たちがカンフーの修業を続ける「稽古」、2003年の重症急性呼吸器症候群(SARS)発生前後、食堂の一隅で若者らがスマホで株、不動産の値動きに熱中する「ぼろ儲け」など、エピソードは多く香港の社会が本来持っていたはずの明るく自由な空気に溢れていた。
返還が近づく80年代、少女だけが英国に移住する恋人たちの「別れの夜」にしても、そこには乾いた悲しさがあるだけだった。
しかし、返還からすでに20年が過ぎた2018年の旧正月を前に英国から里帰りした家族の「道に迷う」には、時代が変わって「あったはず」の自由な空気が徐々に消えていく重苦しさがあった。
中年の男は香港島・中環(セントラル)の雑踏に立つが、見慣れた映画館もシティホールも見当たらず、喧噪さにただ翻弄されるだけだった。
スターフェリーの新設された波止場近くで煙草を吸おうとして「禁煙だ」と注意され、男はただ佇むだけだった。
男は故郷で死を迎える。
散骨された浜辺の先の海にはマングローブの群落があった。
2019年の「逃亡犯条例改正案」反対デモが続く街で、『少年たちの時代革命』は生きる意味を失った少女を救おうとする若者たちを追う。
少女を捜し回る九龍地区の下町は古びた商業ビル、マンションが立ち並び、路地は狭く、見上げても空はいつも小さく切り取られていた。
一人の自殺を思いとどまらせるか、多くの仲間たちのデモに加わるかに揺れる若者たち。
グループの少年は外国に移り住むことが決まっている彼女に「将来のある者は外へ行け」「希望のない者は香港に残る」と語る。
少女は最後に香港に留まることを告げるが、少年の思いの奥底に潜む絶望に暫し、ストーリーを追いかけることを忘れた。
この年の11月、デモに参加した学生、市民らが警官隊に九龍地区・尖沙咀(チムサーチョイ)の香港理工大学構内に13日間包囲され、1377人が逮捕された事件があった。逮捕者のうち未成年者は318人、最後に構内で逮捕された若者らは810人だった。
大学の中から撮影されたドキュメンタリー『理大囲城』は、私が記者時代を送った返還前後には想像もできない「闘い」の記録だ。
撮影者は名前を明かしていない。
学生たちは火炎瓶、石、アスファルト、レンガを投げて脱出を試みるが、警官隊の無差別の催涙弾攻撃は圧倒的だった。
構内ではだれもがヘルメットを被り、防護マスクをつけていた。
顔にはモザイクがかけられ、わずかに目だけが表情を持っていた。
「家に帰りたい」「いつ帰れるのか」と話す声が度々聞こえてくる。
ごく普通の自由な社会、生活を求めただけの若者たちはいつの間にかドラマでしか見たことのような世界に投げ込まれてしまっていた。
大学はビクトリア港の下を通って香港島に抜けるトンネルの出入口に建つ。
大学の横には高架道路が何本も走っていた。
道路に飛び降りる少年をバイクで助け出す「親」と呼ばれたドライバーがいた。
未成年者の救出に駆けつけた中学の教師たちもいた。
ご飯をつくるだけに来ていた主婦のいたことも後で知る。
事件は孤立した「闘い」ではなく、香港社会そのものの「異議申し立て」だった。
映画を見終わって、息苦しさを覚えるままに映画館を出る。
東京の冬の空の青さがとてつもなく得難いもののように思えた。
香港は熱帯の北端に位置するが、晩秋から冬にかけては時に氷が張るような冷え込みにも見舞われる。
寒さに慣れていない人たちは全身をコートで包み込むようにして歩いていた。
何気なく見ていた光景が映画のひとコマ、ひとコマにオーバーラップしていく。
いまも香港で暮らす顔見知りの人たちのことを思った。
香港を去った人もいた。
「新年」を前に香港人の伴侶と共に日本に帰ってきた友もいた。
 ホーム
ホーム ご注文方法
ご注文方法 カートを見る
カートを見る お問い合わせ
お問い合わせ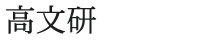
 関連書籍
関連書籍











