- NEWS
アジア新風土記(34)モンスーン

|
著者紹介 津田 邦宏(つだ・くにひろ) 1946年東京生まれ。早稲田大学法学部卒業。72年、朝日新聞社入社。香港支局長、アジア総局長(バンコク)を務める。著書に『観光コースでない香港・マカオ』『私の台湾見聞記』『沖縄処分―台湾引揚者の悲哀』(以上、高文研)『香港返還』(杉山書店)などがある。 |
アジアの風土が木が草が土が雨を運んでくるであろう空気の微妙な
湿りを感じ始めると、やがてモンスーンの季節がやってくる。
アジアに暮らして、あるいは歩いて、この雨季のころが好きだった。
モンスーンは5月ごろになってアフリカ東海岸からインド、
東南アジア、東アジアまで流れ込む高温多湿な季節風だ。
「アジアモンスーン」とも呼ばれ、
南アジアでは「サイクローン」という別名がつく。
アラビア語で「季節」を意味する「マウシム」が語源とされる。
雨はあるときは朝早くから間断なく降り続け、
ときに激しくときにやさしく大地を潤していく。
あるときは日が昇ってからの強い陽光を湧き上がる雲が遮り、
真っ暗になった闇から矢のような雨を降らす。
アジアは雨を友達にしてくれる。
ネパールの丘陵地帯でチベットからの交易路を歩いているとき、
激しい雨に見舞われたことがあった。
傘とか雨合羽はすでに用をなさない。
スケジュール的に次の目的地まで歩かなければならなかったので、
雨宿りの余裕はなかった。
雨の中を歩いていると次第に気持ちが高揚してきたことを覚えている。
最初は上着もズボンもすべてびしょ濡れになったが、次第に体全体から
湯気のようなものが立っていった。
一歩ごとにリズムが生まれ、思わず笑いながら、
大声で歌を歌いながら歩いていた。
乾季が終わろうとしていたインドの平原を汽車で旅したときは、
ただただ赤茶けた大地が広がっているだけだった。
地面は干からび、所々の大きな水たまりは澱み、
川はわずかな流れを辛うじて保っているかのようだった。
森も林も木々はくすんだ葉をしていた。
雨季になって、再び車窓から見る眺めはどこもかしこも一面の水で溢れ、
木々の緑は生き生きと光っていた。
どこが沼でどこが川なのか。
赤茶けた大地はどこにもなかった。時々通過する町の水牛、
農村の水牛は以前のようなやせ細った姿ではなかった。
乾季と雨季の違いはこうまで辺りの風景を一変させてしまうものかと思った。
バンコクではよく、部屋から雨をただじっと眺めていた。
空の黒さ、雨に打たれて変化する木々の緑、
そして雨を浴びる茶褐色の土、それぞれが自身の生命力を雨に抗いながら
競って輝いていた。
柔らかな潤いのある世界はインドで見た過酷な変容とは大きく異なっていた。
その相違は生活する人たちの感性をもまた変えていくのだろうか。
インドの映画監督、サタジット・レイが1930年代の
インド・西ベンガル地方の農村に暮らす夫婦と姉弟の一家4人を描いた
『大地のうた』に、乾季が明けて雨が降り出す光景がある。
蓮沼にアメンボが波紋を広げていく。
暗くなった空に雷鳴が轟き、雨がポツリ、ポツリと落ちてくる。
水連の葉、蓮の葉が風で翻り、驟雨(しゅうう)が大地に突き刺さってくる。
水辺で姉は髪をとかし、顔一面に雨を浴び、踊り始める。
しばらくして木陰で「雨よやめ、雨よやめ」とつぶやいた。
雨の中で踊った後、姉は高熱を出して嵐の夜が明けたとき息を引き取る
。
監督は125分の映画に一度だけ登場させた「雨」に
どのような役割を与えたのだろうか。
雨季の始まりを告げる雨に、命の躍動と厳粛な死を託したかったのか。
モンスーンはアジアという巨大な人口密集地帯を豊穣な大地へと変えていく。
雨季が続く半年の間、農村に広がる水田は米作の実りが
2回でも3回でも可能になり、海、沼では魚湧くほどの魚介類が育っていく。
雨と風の日々の襲来は人々の日常生活の一部になり、農民も漁民もそして
町の人もすべてが豊かな水とともに生きていた。
モンスーンはまた突然の死を運んでくる。
そのことも人々は許容しなければならなかった。
バングラデシュ南部のチッタゴンにサイクローンの後に入ったときのことだ。
ガンジス川などの巨大三角州の一画にある町は高台の高級住宅街に被害は
ほとんどなかったが、ベンガル語で「ゴリブ・マヌーシュ」と呼ばれる
貧しい人たちの住む海抜ゼロメートル地帯は逃げ場がなかった。
毎年繰り返される洪水と高波に、助かった人が翌年も生き延びるという
保証はどこにもなかった。
雨に対する感覚はしかし、都市と田舎で次第に乖離していくようにも思う。
農漁業に直接かかわらない都会の人たちにとって、
雨はすでに「雨乞い」という言葉が象徴するような
天に祈るという感情とは無縁の負の存在になっているのではないか。
雨傘が都会生活の必需品になったのはそんな昔の話ではなく、
バンコクの友人は「雨の降り方が変わってきた。
以前は少し経てば上がったのに」と話してくれたことがあった。
日本人の多くが毎日の天気予報に晴れの日を求め、雨が降るのを疎ましく思うようになる気持ちと、どこか通じるものがあるのかもしれない。
シンガポールにコロニアルスタイルの瀟洒なホテル、ラッフルズホテルがある。
カクテルのシンガポール・スリングで知られる「ロングバー」で
雨をやり過ごしながら、英国の作家、サマセット・モームのことを思った。
彼はこのホテル、バンコクのマンダリンホテルに滞在、
画家のゴーギャンを題材とした『月と六ペンス』などを書いた。
『雨』という短編がある。
南太平洋サモア群島のパゴパゴという港町での話だ。
任地に赴く途中、麻疹で逗留を余儀なくされた志操堅固な宣教師が
同じ船に乗り合わせた娼婦を改心させようとして
最後はその女性の肉体に負けて自殺する。
「あのしとしとと降る英国のような雨ではないのだ。無慈悲な、なにか恐ろしいものさえ感じられる。人はその中に原始的自然力のもつ敵意といったものを感得するのだ。降るというよりは流れるのである。まるで大空の洪水だ。神経も何もかきむしるようにひっきりなしに、屋根のナマコ板を騒然と鳴らしている。まるでなにか凶暴な感情でも持っているかのように見える」(中野好夫訳、新潮文庫、1959年)
雨が降り続かなければ事件は起きなかったのか。
白人の宣教師が雨への畏敬の念を持っていなかったからか。
あるいは雨を友達にすることができなかったからなのか。
『雨』は初版のときは娼婦の名前「サディ・トムソン」が
題名に使われた(守山義雄、世界名作の旅、朝日選書、1988年)。
モームはなぜ、タイトルを変えたのか。
雨を事件の主役にしたかったのだろうか。
 ホーム
ホーム ご注文方法
ご注文方法 カートを見る
カートを見る お問い合わせ
お問い合わせ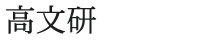
 関連書籍
関連書籍











