- NEWS
アジア新風土記(29)マルコス2世のフィリピン

|
著者紹介 津田 邦宏(つだ・くにひろ) 1946年東京生まれ。早稲田大学法学部卒業。72年、朝日新聞社入社。香港支局長、アジア総局長(バンコク)を務める。著書に『観光コースでない香港・マカオ』『私の台湾見聞記』『沖縄処分―台湾引揚者の悲哀』(以上、高文研)『香港返還』(杉山書店)などがある。 |
アジアを歩いていると、様々なところで様々なフィリピンの人たちに出会う。
香港の公園には休日に故郷の話を語り合うアマたち(家政婦)がいた。
台北ではカトリック教会のミサを終えた工場労働者が裏通りのフィリピンバー
で瓶ビールの「サンミゲル」を傾けていた。
シンガポールのホテルのクラブはバンドとシンガーが客を酔わせていた。
バンコクの出入国管理事務所はビザの問い合わせをする英語家庭教師が詰めか
けていた。
しかし、1億1千万人の国民の50人に1人ともいわれる海外出稼ぎ労働者たちから
はフィリピンという国家、国の形がなかなか見えてこない。曖昧な国家像はかつ
てフィリピン国軍のクーデター、大統領選、あるいは日本人誘拐事件、日本での
活躍を夢見る少女たちのダンス教室などを取材したときにも感じたことだ。
台北の教会でミサを終えたフィリピン人たち
フィリピンは16世紀にスペインが支配する以前の歴史資料に乏しく、代わって
植民地とした米国統治のときも見るべきものはわずかだった。
第2次大戦後、独立国として新たな歩みをスタートさせたが、まとまった一つの
国の在り方を十分に描き切らないまま今日まで来たようにも思える。
海外でも国内でもフィリピーナは生き生きと暮らしているのに、強烈なナショナ
リズムのにおいを感じることはなかった。
1986年2月の「ピープルパワー革命」は国家と国民が一つになってフィリピンと
いう国の存在をアピールしたときだ。
直前の大統領選でマルコス氏が当選を宣言したが、市民らが不正と選挙無効を訴
え、国軍の反乱も加わる。
100万人ともいわれる抗議デモにマルコス氏はハワイに亡命、民主勢力に推され
たコラソン・アキノ候補が大統領に就く。
アキノ氏のフィリピンは新時代を生み出すことはできず、その後ドゥテルテ氏ま
での5人の大統領もまた明確な国家像を提示することはなかった。
大きな変化のなかった35年余り、経済はそれでもそれなりに成長してきた。
1千万人を超える海外居住者からの送金は年間300億ドル前後になり、国内総生産
(GDP)の1割近くを占めるまでになった。
外国企業のコールセンター基地などのサービス業も活発化、経済成長率は6%の伸
びを見せている。ただ、極端な貧富の格差、不平等社会は変わらず、スラムのご
みの山から拾った残飯を再調理した「パグパグ」を日々の糧とする人たちはなく
ならなかった。
2022年5月9日、6年に1度の大統領選が行われ、マルコス元大統領の長男フェル
ディナンド・マルコス元上院議員(64)が当選する。
副大統領には強権政治に終始したドゥテルテ現大統領の長女でダバオ市長の
サラ・ドゥテルテ氏(43)が選ばれた。独裁と強権の国家を築いた父親たちの跡
を継ぐ二人の政権が始まる。
マルコス氏が獲得した3102万票(10日選管非公式集計・開票率98・03%)は
2位の現副大統領レニ・ロブレド候補(57)の2倍以上になった。
これほどの圧倒的な支持はどこから来たのか。
マルコス独裁体制を知らない18歳から41歳までの若い有権者が全体(約6700万
人)の56%を占めるほか、元大統領とその時代に郷愁を感じる人たちが
「強いフィリピン」の再来を2世に求めたからだろうか。
「ピープルパワー革命」さえもマニラ首都圏の出来事であり地方はほとんど関係
なかったという気持ちが少なからぬ人たちの心に残っていたということだろうか。
ドゥテルテ氏の「麻薬戦争」は継承されるのか。
「トクハン」と呼ばれる捜査は疑いが少しでもあれば証拠が不十分でも取り締ま
りを強行、抵抗すれば射殺も容認した。
証拠主義に則る現代の警察とはおよそかけ離れた捜査だった。
この6年間の死者は6千人を超え、21年ノーベル平和賞を受賞したウェブメディア
「ラップラー」のマリア・レッサ氏らが批判を展開、国連からも非難が続いていた。
ミンダナオ島の自治政府問題もある。2014年、政府と分離独立武装勢力が包括和
平で合意、19年にはバンサモロ基本法制定に基づくバンサモロ暫定自治政府が設
立された。
暫定自治政府は武装勢力モロ・イスラム解放戦線のほか、キリスト教団体、民間
企業、女性グループなどの各セクター代表80人で構成されたが、フィリピン政府
の中での自治政府の役割はまだ確定していない。
モロ・イスラム解放戦線の約4万5千人といわれる兵士の武装解除も難問だ。
サラ・ドゥテルテ副大統領はミンダナオ最大都市ダバオの市長を務めていただけ
に、積極的な役割を担うとみられるが、平和裏の進展がなければ、和平プロセス
は後戻りしかねない。
東南アジア諸国連合(ASEAN)と中国が「行動規範」の法的拘束力をめぐって対
立する南シナ海の領有権問題もまた懸案事項だ。
フィリピンは2012年、ルソン島から西200キロのスカボロー礁付近での中国漁船
操業をめぐって中国と衝突、フリゲート艦を派遣したが、中国は監視船を同礁付
近に常駐させた。
2013年1月、ベニグノ・アキノ3世大統領は国際仲裁裁判所に提訴、16年には中
国の「南シナ海は歴史的な領有海域」との主張に根拠なしの結論が出る。
ドゥテルテ政権はこの結論を基に中国への強硬姿勢を見せることはなく、対中貿
易などの交渉カードとして使うだけで積極的に動くことはなかった。新政権がど
のような対中政策をみせるかはまだ不透明だ。
中国の南シナ海「進出」を容易にした遠因の一つに、フィリピンと米国の関係悪
化が挙げられるかもしれない。
米国は戦後、フィリピンとの軍事基地協定によってマニラから北西60キロのクラ
ーク空軍基地とスービック湾の海軍基地を使用、南シナ海への軍事プレゼンスを
確保していた。
使用期限延長交渉中の1991年6月、空軍基地から16キロのピナトゥボ火山が大噴
火する。基地は15センチ以上の火山灰が積もり、全長3千200メートルの滑走路
2本はじめすべてが機能マヒに陥った。
米軍は空軍基地を放棄、海軍基地もフィリピン上院の拒否によって撤退を余儀な
くされた。
中国は「軍事的空白地帯」になった南シナ海の「内海化」政策を確実に進めてい
く。米軍のフィリピン駐留は2014年に再開されたものの、両国の同盟関係はいま
も不安定なままだ。
火山灰で埋まったクラーク米空軍基地。後方の噴煙を上げるピナトゥボ火山は噴火で
頂上部分が吹き飛び、標高は250メートルほど下がって1486メートルになった。
ナ海の状況はどうなっていたかと思うときがある。
 ホーム
ホーム ご注文方法
ご注文方法 カートを見る
カートを見る お問い合わせ
お問い合わせ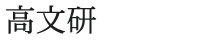
 関連書籍
関連書籍











