- NEWS
アジア新風土記(13) 台湾の新学期

|
著者紹介 津田 邦宏(つだ・くにひろ) 1946年東京生まれ。早稲田大学法学部卒業。72年、朝日新聞社入社。香港支局長、アジア総局長(バンコク)を務める。著書に『観光コースでない香港・マカオ』『私の台湾見聞記』『沖縄処分―台湾引揚者の悲哀』(以上、高文研)『香港返還』(杉山書店)などがある。 |
台湾の新学期は9月から始まる。台北で2013年から2年ほど暮らしていた時、近くに小学校があった。あたりの空気が心持ち爽やかになってくる頃、子どもたちが学校に戻ってくる。新1年生を上級生が見守りながら集団登下校する姿、交差点で児童を誘導する父母らは日本でも見慣れた景色だった。車、バイクで送迎する保護者が多いことが違っていた。
どの小学校にも校門近くに必ず「家長接送区」がある。児童を待つ父母らの待機場所だ。顔馴染みの人たちはしばらく世間話をした後、校門から出てくる子どもと連れ立って帰っていく。毎日の顔合わせはいつしか「家長接送区」を小さなコミュニティーに変えていく。学校を中心とした保護者らの交わりが幅広く豊かだと思った。
台湾の親たちが過保護だというわけでもないようだ。親たちが子どもを送り迎えする光景は1987年に38年間続いた戒厳令が解除され、社会に「自由の風」が吹き始めたころから目立つようになったと聞いた。急激な自由化は時に無秩序な世相を生み出す。犯罪が増え、一攫千金を目論む誘拐事件も少なくなく、裕福な家庭は高級外車から安い車に乗り換え、タクシー運転手は強盗に備えて自衛の銃を持つようになった。親たちの一種の自衛策は、民主化が進んで社会に落ち着きが出てからも「習慣」として残ったのかもしれない。
何気ない日常の風景も、その背景にはいくつもの歴史の痕跡が折り重なっていた。
「家長接送区」の親たちはなんの気兼ねもなく台湾語(閩南語・びんなんご)で話していた。戒厳令下では役所、学校など公の場で使うことが禁じられ、わずかに家の中でしか話すことが出来なかった言葉だ。中国語だけが公式言語の時代だった。台湾語は大陸から台湾に移ってきた人たちの多くが使っていた福建省南部・閩南地方の言葉に由来する。台湾の人たちの日常語であり、約4人に3人が話すといわれる。
台湾の民主化は台湾の人たちが「台湾人意識」を育んでいくことで確かなものになっていったが、そのバックボーンには台湾語の復権があった。
民主社会に道筋をつけた李登輝元総統が2020年7月に死去してから1年余が過ぎた。台湾人初の総統として台湾人を主体とした台湾化政策に腐心、教育の現場にも「台湾」の存在を持ち込んだ。自分たちが実際に暮らしている所の歴史を知らなくては、という考えに基づいた「認識台湾(台湾を知ろう)」という教科書の作成だ。
1997年9月、李総統はすべての中学1年の授業に台湾の歴史、地理、社会の3部門に分かれた「認識台湾」の採用に踏み切る。従来の歴史教育の抜本的な改革だった。国定教科書は2003年の制度改革で検定制に変わり、その内容は小中一貫教育となった新課程の「社会領域」に組み込まれる。
中国共産党との内戦に敗れて台湾に逃れた中国国民党の眼目は同党を正当な後継とする大陸の王朝史と大陸の地理の学習であり、台湾の人たちの生活を支えてきた言葉と文化、歴史などは封印された。そこに日本の植民地時代、台湾総督府が台湾人に日本語教育を徹底させ、台湾の文化、歴史を学ばせなかったことに通ずる支配者の統治スタイルをみる。
「認識台湾」はまた、日本についてこれまでの教科書が主に紹介してきた日本軍の大陸侵略、抗日運動だけではなく、50年間植民地とした台湾での皇民化運動、理蕃政策、農業改革、公衆衛生活動から台湾籍日本兵まで多岐にわたって語っていくことで新たな視点を提示、教室では台湾そのものについての知識だけでなく、日本、世界、そして大陸への異なる発想、アプローチが培われていった。
『台湾の歴史教科書における日本認識の一考察―「歴史」と「認識台湾」を中心に』(張原銘、立命館産業社会論集第38巻第3号、2002年12月)は日本への理解について「近現代台湾が歩んできた独自の歴史を振り返ることから始まる」と書く。「日本による植民統治、オランダによる統治時代、清朝による統治時期、国民党による統治時期と並列に並べて、相対化していく作業の中から、はじめて客観的な認識が可能になるだろう」
2013年、中国国民党の馬英九総統時代にある論争が起きる。日本の植民地時代を日本が統治した「日治」と表現するか、日本によって占拠された「日拠」とするかの争いだった。「認識台湾」は「日治」といういわば「歴史的事実」に沿っていたが、公文書などに「日拠」という言葉が使われていたことが明らかになる。論争は16年に民進党の蔡英文氏が総統に選出されてからは持ち上がっていない。国民党総統になった場合の再燃は否定できないが、「認識台湾」を学んだ人たちに「日拠」は説得力を持ち得るかどうか。
台湾と同じように9月に新学期を迎える国は多い。その一つである中国で21年もまた少数民族への中国語教育徹底方針が打ち出された。
8月2日、中国教育省は55の少数民族が暮らす地域などの幼稚園児に対して、標準中国語での教育を行うよう通知した。幼稚園教師にも一定レベルの中国語習熟を求めるという。「実施」に反対するなどの動きは伝わってこない。
少数民族の「沈黙」は内モンゴル自治区でも続く。20年9月、中国政府は民族学校の小学1年、中学1年のモンゴル語での授業を中国語に変更した。子どものモンゴル語能力が落ちるのは目に見えていた。懸念する父母らは授業ボイコットなどで抗議したが、警察当局によるデモ参加者の公開、抗議SNSの削除などで抑え込まれる。全人口2400万人の自治区でモンゴル人は2割弱しかいない。持続的な抵抗運動は不可能に近い。
少数民族の中国語教育強化は新疆ウイグル自治区、チベット自治区で導入されており、内モンゴルもその延長線上にあった。どの自治区でも漢人の流入は止まらず、ウイグル族、チベット族の言葉もまた失われつつある。民族の言葉を奪うということは民族の文化、歴史を奪うことにつながっていく。
21年8月27、28日、北京で中国共産党中央民族工作会議が開かれ、習近平国家主席は「中華文化が幹、各民族の文化は枝と葉だ」と述べた。国営新華社通信はさらに「各民族の民族意識は中華民族共同体意識に従い奉仕する」という主席の言葉を伝える。少数民族の文化は「枝葉」にすぎないのか。「中華民族への一体化」政策はどこまでいくのか。
 ホーム
ホーム ご注文方法
ご注文方法 カートを見る
カートを見る お問い合わせ
お問い合わせ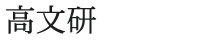
 関連書籍
関連書籍












