- NEWS
アジア新風土記(119) 遠いイラン

|
著者紹介 津田 邦宏(つだ・くにひろ) 1946年東京生まれ。早稲田大学法学部卒業。72年、朝日新聞社入社。香港支局長、アジア総局長(バンコク)を務める。著書に『観光コースでない香港・マカオ』『私の台湾見聞記』『沖縄処分―台湾引揚者の悲哀』(以上、高文研)『香港返還』(杉山書店)などがある。 |
イランでいま何が起きているのか。
2025年12月末から26年1月、悪化する経済への不安がストライキを生み、さらに反政府デモへと広がっていった「事件」は、混乱下の錯綜する情報のなかで、その実相に迫るには限りがあった。
日々断片的に伝えられるニュースにもどかしさを感じるとともに、人々の日常はどのようなものだったか、暮らし向きはどこまで苦しくなっていたか、あるいはイスラム国家の自由度に変化は生まれたのかなど、ほとんど知らないことばかりだと、改めて遠いイランを思う。
12月28日、テヘランの中心街にある最大の市場「グランドバザール」の商人たちはイラン・リヤルの下落、慢性的なエネルギー不足の中で政府の有効な経済政策を求めて声を上げ、店を閉鎖するなどの行動を起こす。街はインフレによる食料品をはじめとする生活必需品の高騰が市民生活を圧迫、不満がいつ爆発してもおかしくない毎日が続いていた。大学生、市民らが同調、抗議の波はテヘランからシーラーズ、マシュハドなどの地方中核都市へと拡大していった。
6月のイスラエルとの武力衝突と米国による核関連施設爆撃に、「イランという国」はどうなるかという漠然とした危機感もデモに駆り立てる一因になったのではないか。
経済的な要求がいつ、ハメネイ師を最高指導者とする政教一致のイスラム国家体制批判に転化していったのか。街頭に飛び出し、集まり、商店やモスクなどに火を放って気勢を上げ、「ハメネイに死を」「独裁者に死を」といったスローガンが飛び出すまでにそれほどの時はかからなかった。
1979年のイラン革命によって倒されたパフラヴィー朝・パーレビ国王の長男で米国に亡命中のレザー・パーレビ元皇太子(65)が自宅、路上でスローガンを叫べと呼びかけたことも、これまでにはなかったことだ。
元皇太子が革命時に国外に逃れてから47年が経つ。革命後に生まれた世代が圧倒的に多くなっている現在、どれほどのインパクトを与えられたかという気もする。
2026年1月8日から9日にかけて抗議行動は最も激しくなり、政府はインターネット、電話回線を全面的に遮断、デモの連絡、情報交換、国外サイトの閲覧を封じることで対抗する。イスラム革命防衛隊などの鎮圧の動きも苛烈を極めた。当初こそ催涙ガス弾でデモ隊を解散させていたが、次第に至近距離からの実弾使用に切り替え、狙撃兵まで投入されたとの報道も流れた。
圧倒的な武力の前にデモは次第に勢いを失っていき、ほとんどの都市からシュプレヒコールの声が消え、人々は沈黙を余儀なくされる。
29日の英ロイター通信はイラン国内の活動家の話として、当局がデモの再燃を防止するために直接関係ない人たちを含めた数千人を拘束していると伝えた。
イラン国営テレビは21日、一連の抗議デモで3117人が死亡したと発表する。政府の公式発表とも言える死者数が事実かはわからない。
米国に拠点を置く人権団体の通信社HRANAによると4902人の死亡が確認されたという。米タイム誌ウェブサイトは25日、「独自には検証できない」としながらも「イラン保健省高官の話では全土の街頭で約3万人が死亡した可能性がある」と報じた。情報元の「立場」によって数字が独り歩きしかねないことを踏まえてもなお、犠牲者の多さに驚く。
大規模な反政府デモと犠牲者数は国家権力によって常に恣意的に総括され、政府・治安当局の徹底的な隠蔽工作は正確な検証を極めて難しくさせる。
イランの事件にかつて朝日新聞記者として1989年の中国・天安門事件を東京から追っていたときを思い起こす。
北京の天安門広場で何が起きているのか、負傷者が出たのか、死者は何人になったのか。
情報は毎日、昼と夜とでも変わり、北京に幅広いネットワークを持つ香港メディアの報道などを頼りに取材を続けた。北京特派員からの情報とその他メディアからの情報との整合性に時間を費やして一日が過ぎていった。
中国政府は事件を「暴乱」と断じる。そこに学生らの民主化への訴えを一顧(いっこ)だにしない権力者の独善と傲慢をみる。死者319人という公式発表には、実際は数千人の死者だったという推定もある。真相は40年近く経っても確かめる手立てはない。
イランでは2022年9月、テヘランの若い女性がヘジャブ(スカーフ)の被り方に問題があるとして警察当局に逮捕され、その直後に死亡したことをきっかけに「ヘジャブデモ」が起きた。
「女性、命、自由」というスローガンを掲げてハメネイ師らを批判するデモは首都から地方都市に及んだが、社会変革には程遠く、当局の圧力にあらゆる言動が封じ込められた。国連人権理事会調査団による死者551人という調査結果は、公開されている情報、被害関係者らの聞き取り調査などからまとめたものだ。
イラン政府への再三の協力要請に回答はなかった。死者数は「最低でも」という但し書きがあると理解すべきだろう。(『アジア新風土記41』参照)
ヘジャブデモから3年3か月後、街頭デモにストライキも加わった今回は商人、労働者、学生、女性、少数民族・クルド族など多種多様な人たちが参加したが、それでも最高指導者退陣などを勝ち取ることはできなかった。
度重なる挫折の中で得たものは何だったのか。
絶望を跳ね返すだけの力は残っているのだろうか。
イラン政府は26年2月6日、米国政府と核開発問題などを巡る高官協議をオマーンで行った。協議の開催は米国がイランの現体制存続を前提としていることを示し、反政府デモが外交の場で突き詰めて話し合われた様子は窺えない。国際社会に半月ほどに少なくとも3千人を超す市民らが殺害された事件を問う動きもまた、ない。
3月の春分の日、イランでは「ノウルーズ」と呼ばれる正月を迎える。イラン暦の新年だ。古代ペルシャのゾロアスター教の祝祭に由来するともいわれ、年末は絨毯、床、窓などの大掃除を終え、小麦の芽、リンゴなど7つの縁起物を集めた「ハフト・スィーン」という正月飾りを準備する。イランの人たちにとって26年は、暗く悲しい年明けになる。
 ホーム
ホーム ご注文方法
ご注文方法 カートを見る
カートを見る お問い合わせ
お問い合わせ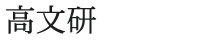
 関連書籍
関連書籍











