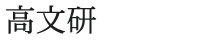- NEWS
アジア新風土記(117) 玉への想い

|
著者紹介 津田 邦宏(つだ・くにひろ) 1946年東京生まれ。早稲田大学法学部卒業。72年、朝日新聞社入社。香港支局長、アジア総局長(バンコク)を務める。著書に『観光コースでない香港・マカオ』『私の台湾見聞記』『沖縄処分―台湾引揚者の悲哀』(以上、高文研)『香港返還』(杉山書店)などがある。 |
中国の人たちと日々の日常を過ごしていると、彼らの玉への限りない想いを感じるときがある。自宅に飾ってある玉の置物を愛おしく眺めるとき、食事中に何気なく玉の腕輪に優しく手を添えるとき、玉と共に生きてきた人たちの愛情の深さにふと、気づかされる。その深さの度合いを推し量るのはとても無理のことのように思えた。
台北の中心部を南北に走る建国南路の高架下は週末になると建国仮日玉市が開かれる。
1989年に開場してかれこれ40年近くになる。長さ200メートルほどの玉市には200を超す店が縦横3メートルあるかないかの陳列台に玉の仏像、数珠、指輪、腕輪、ペンダントなどを並べて客を誘っていた。
年代物から今風に細工されたもの、大陸産、台湾産などがそれぞれに美しさを競い、色もまた緑、茶、黄、赤と変化に富んでいた。天井は低く、ライトもそれほど強くない中、訪れた人たちは台と台の間の狭い通路に肩をぶつけ合いながら行き来して気に入った玉を探す。
中国の人は手に取った玉を眺め透かしてみる目に迫力があり、一つ一つを品定めしながら歩いているようだった。そのこだわりは、地元の人も大陸からの観光客も変わりはなかった。中国人以外の旅行者は玉市の雰囲気を楽しみながら時々止まって玉を眺めるので自然とスムーズな流れになっていく。
建国仮日玉市。平日は駐車場になる
建国玉市
建国玉市
玉石混合の世界に勇んで入ってきた人たちの熱気にいささか気圧(けお)されて市を出ると、目の前には同じ高架下に続く花市があった。生気に溢れた草花、木々の清々しさに、思わず大きな息をした。
建国玉市と同じような市は香港にもある。九龍半島・油麻地(ヤウマテイ)の繁華街の一角にある玉器市場(ジェイドマーケット)は、畳一畳ほどの小さな陳列台が400ほどあり、翡翠、紅玉、黄玉などあらゆる色に彩られた玉が並んでいた。
客は自分の小物を求める人からプロの目利きまで様々だ。陳列台一杯に無造作に広がる玉からどうやって真贋を見分けるのか。素人ではないと思われる人に聞いてみたことがあるが、ひまなときにぶらっと来て掘り出し物を探すと言っていた。「儲けものはほんのたまにだけど・・・」と屈託のない笑顔だった。
香港のジェイドマーケット
ジェイドマーケットから少し南に下がった広東街には中国返還前は玉の原石を売り買いするプロたちの市が立っていた。顔を出す人たちは決まって男衆だった。
100人はいただろうか。自慢の「石」を大事そうに抱えている男、路上に置いて動かない男たちがいた。女性はいなかった。石は外から見るとふつうの石の塊だった。ただ、一カ所だけがカットされ、中の玉がのぞいていた。商いは上着の下にお互いの手を入れ、その指の動きで決まる。値段がうまく折り合えたかどうかは男たちの表情でわかった。返還後からすでに四半世紀以上が経って、同じような市が続いているかはわからない。
広東街の原石は多くが翡翠(硬玉)か
玉に魅了される中国人の気持ちは身分の貴賎を問わず古代中国から受け継がれてきた感性といっていいのかもしれない。紀元前の西周(BC1100~770)のころには玉を死者に携えると遺体が一千年以上腐敗しないと信じられ、耳、口などに玉製品を詰める風習が生まれる。
1968年に出土した西漢時代の中山王、劉勝とその妻、竇妃の衣装は薄く削った玉を金糸で縫い上げた「金縷玉衣(きんるぎょくい)」として知られ、河北省石家荘の河北博物院に所蔵されている。博物院に訪れる人は金縷玉衣をどう思うのだろうか。羨ましいと感じるのか。叶う事なら自分もあの衣装を身に着けて旅立ちたいと願うのか。
中国の玉は軟玉(ネフライト、閃玉)が一般的で、いわゆる翡翠と呼ばれる硬玉(ジェダイト、輝玉)とは異なる。硬玉は主にミャンマー、雲南省で産出され、清朝の頃にようやく軟玉を凌ぐまでになり、台北・故宮博物院の翠玉白菜のような逸品を生む。
『天工宝物―八千年の歴史を物語る長河』は
「乾隆時代晩期以降、翡翠は人々に最も好まれる玉となりました。温かく潤った穏やかな性質の玉よりも、人々の目を奪う艶やかな光沢を放つ玉が好まれるようになり・・・」
と書く。(国立故宮博物院、2007年)
人々の軟玉への愛着はしかし、いまも失われていない。玉は軟玉であろうと硬玉であろうと持ち主に幸運をもたらし、あらゆる危害から守ってくれる護身であり、金銭的な価値とは無縁のものだと聞いたことがあった。
日本では玉と言えば、糸魚川地方で産出される翡翠を連想して、軟玉にはあまり関心がない。単に「宝石」とみるからではないか。古代には勾玉というものがあったが、いつしか神秘的な力が消えていき、日本人の心に長く留まることはなかった。その違いはどこに由来するのだろうか。
軟玉は新疆ウイグル地方のホータン産が随一とされる。南の崑崙山脈からの雪解け水がもたらす崑崙石の中で、羊脂色の玉は羊の脂肪のような滑らかさと深い光沢をもって珍重されてきた。中原の歴代王朝に玉が運ばれる道はシルクロードの時代よりも遥か昔から「玉の道」と呼ばれていた。荒涼とした砂漠のオアシス都市で商われた原石が磨き抜かれ、やがては王朝の貴人たちが身に纏う金縷玉衣になるまでの変転を思う。
そのホータンでいまも香港・広東街と同じように玉の原石を売買する市が立っていることを知る。(『疾走!タクラマカン砂漠鉄道~冬のシルクロードをゆく~』NHKBS、2025年5月3日)
青空の下、人だかりがあちらこちらにでき、だれもが原石の値踏みに余念がなかった。大石を抱えて歩き回る人、陳列台に小さな石を並べる人、路上に石を広げる人がいた。売り手のほとんどはウイグル人だ。買い手は北京、上海などから来た漢人が多いという。
中国元の札束を持ち歩く人、携帯電話に原石を写して顧客と相談する人がいた。市に集まった人たちの玉に惹かれた表情は香港で会った人たちと似ていた。ただ、広東街の男たちは狙った石を手に入れた興奮、高値で売り損なった失望を剝き出しにして、より人間臭かった。現代のホータンはそれだけドライにシステマティックに商いが進んでいるということか。
ホータン郊外を流れるユルンカシュ川の河原には深さ1メートル以上もの穴を掘っている人たちがいた。水量が少なくなる秋から冬にかけて、それも深く深く掘らないと玉は見つからないという。河原を歩いて玉を探す風景はなかった。
 ホーム
ホーム ご注文方法
ご注文方法 カートを見る
カートを見る お問い合わせ
お問い合わせ