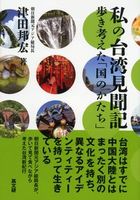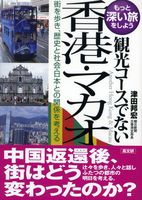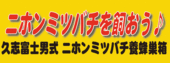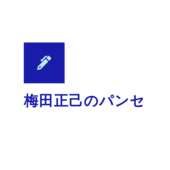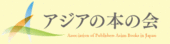- NEWS
アジア新風土記(112) インドネシアの混乱

|
著者紹介 津田 邦宏(つだ・くにひろ) 1946年東京生まれ。早稲田大学法学部卒業。72年、朝日新聞社入社。香港支局長、アジア総局長(バンコク)を務める。著書に『観光コースでない香港・マカオ』『私の台湾見聞記』『沖縄処分―台湾引揚者の悲哀』(以上、高文研)『香港返還』(杉山書店)などがある。 |
インドネシアの首都ジャカルタで2025年8月末に発生した反政府デモは10月に入っても市民、学生らの抗議行動が伝えられ、完全に収まる気配はない。
プラボウォ大統領はデモを国家に対する脅威と位置づけ、強気の姿勢を崩さない。社会の混乱は続くのか。
8月25日、国会議員の手厚い住宅手当に抗議する市民らのデモは一部で政府庁舎、警察署を襲うなど暴徒化、警察部隊と衝突して少なくとも10人が死亡、負傷者は1000人を超えた。
住宅手当は国会議員580人に月5000万ルピア(46万円)を支給するもので、給与、各種手当を合わせると1億ルピアにのぼる。
ジャカルタの最低賃金の9倍を超えるだけに市民、学生らの怒りが爆発した。
28日には配達中のバイクタクシー運転手が警察車両に牽かれて死亡する事件が起き、警察幹部の更迭要求など政府を批判する声はさらに広がっていった。
デモはジャワ島のバンドン、スラバヤ、西部スマトラ島のメダンなど20を超える都市に拡大、中部スラウェシ島マカッサルでは29日、本会議中の議会庁舎が放火されて4人の死者が出た。
大統領は住宅手当の見直しを決定する一方で治安部隊を増強、31日には一連のデモに対して国軍と警察による断固とした取り締まりを表明する。
当局の発表によれば、拘束者は9月8日時点で5444人に上り、逮捕者は24日までに959人に達したという。(『世界を見る眼』ジェトロ・アジア研究所ウェブマガジン、25年10月)
ジャカルタの抗議デモからすでに2か月が過ぎた。
デモ参加者らの拘束が長期化するなかで、事態が今後どのように展開していくかの予測はつかない。1998年に当時のスハルト大統領を退陣に追い込んだような大規模騒乱を憂慮する声も出始めている。(『アジア新風土記53』参照)
プラボウォ大統領は2025年10月20日、就任1年を迎えた。
ジャカルの大統領公邸近くにはこの日も学生ら数百人が集まって抗議の声を上げた。反政府デモがなかなか終息しない背景には市民らの鬱積した思いがある。
この1年の大統領に見るべき成果はあったのか。
公約に掲げた無料給食プログラムは生活に苦しむ人たちの感情を逆なでする。
低所得層支持を目的として25年1月から始まった幼児から高校生までの給食無償化は5年間で約450兆ルピア(約4兆1500億円)という膨大な経費が見込まれる。しわ寄せは省庁、地方政府の予算削減となって跳ね返り、インフラ整備、公共サービスなどへの影響が出ている。地方自治体は財源確保のために8月までに固定資産税を最大1000%引き上げた。
経済の停滞も政府の無策と映る。
25年1月から6月までのレイオフ(一時解雇)は前年同期比で約32%増の約4万2千人にもなった。2月の失業率4.76%は1年前とほぼ変わらず、改善の兆しは見えてこない。
ジョコ・ウィドド前大統領が打ち上げたカリマンタン島東部の新首都「ヌサンタラ」への移転計画はどうなるのか。大統領は就任から一度もヌサンタラを訪れず、前大統領が24年8月にヌサンタラで初めて行った独立記念式典も25年はジャカルタに戻した。総事業費435兆ルピア超ともいわれる首都移転への国民の賛否はなお拮抗している。計画の順調な進展は未知数だ。
市民たちの抗議デモが宗教対立、紛争へと広がっていないことはまだ救いかもしれない。2億8500万人の約87%がイスラム教徒であるインドネシアで、社会の空気は次第にイスラム教的な道徳観に染まりつつある。
22年の刑法改正案は未婚者による婚前交渉、同棲が禁止され、違反した場合は最高1年の禁固刑が科せられなど、イスラム教の教えが色濃く反映された法律だ。
建国当初の仏教、ヒンズー教などすべての宗教に寛容な理想像から離れつつある風潮はどこまでいくのか。改正刑法は26年1月から施行される。モスレムの不満が他宗教の人たちの攻撃へと転化する懸念は消えない。
イスラム過激派の動向も気になる。25年10月12日、バリ島では23年前に起きた爆弾テロ事件の犠牲者追悼式が開かれ、被害者遺族、各国の関係者らが慰霊碑前で祈りを捧げた。
イスラム過激派「ジェマ・イスラミア(JI)」メンバーによる犯行とみられ、繁華街クタの路上に止めてあった自動車爆弾などの爆発で、オーストラリア、日本などからの観光客、島民ら202人が犠牲になる。
JIは24年6月に解散を表明、5か月後には元幹部がジャカルタでの集会で脱過激化と非暴力を訴えた。メンバーらの武器も警察当局への引き渡しが進んでいる。一連の「平和活動」がどこまで言葉通りのものか。人々の心の隙に入り込んでいく恐れは常につきまとう。
ニューギニア島西部パプア地方の分離独立運動もある。
25年10月15日、国軍は独立派「自由パプア運動(OPM)」管理下の村で戦闘員約30人と交戦、14人を殺害、ライフルなどの武器を押収した。OPMはインドネシアによる1963年のパプア地方併合後、独立運動を続ける。
東経141度で国境を接する東部のパプアニューギニアは75年にオーストラリアの委任統治から独立した。
スハルト元大統領時代、国軍はその主な権力基盤だった。国軍幹部だったプラボウォ氏は娘婿としてスハルト独裁体制を支えてきた一人だ。
98年の民主化デモ後、国軍は国防に専念すべきだとする国軍法が制定されたが、大統領就任からまる5か月の2025年3月20日、国会で現役軍人の登用を国軍と関わりの深い10省庁・機関から検察庁、国家防災庁など14省庁・機関へと拡大する改正案が可決される。
正副大統領らへの最高禁錮3年の侮辱罪も改正刑法に盛り込まれた。国軍の政権への「介入」に加えて、恣意的な刑法の運用による民主活動家らへの圧力などが広がるのではという指摘もあった。
社会に不穏な空気が残ったままデモ収拾の道筋が見えないとき、あるいは様々な「火種」のどれか一つでも弾けたとき、国軍は治安維持を名目に反政府運動、批判を抑え込んでいくのか。インドネシアはいま、スハルト後の民主国家の道を歩むか強権国家に戻るかの岐路に立っている。
 ホーム
ホーム ご注文方法
ご注文方法 カートを見る
カートを見る お問い合わせ
お問い合わせ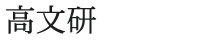
 関連書籍
関連書籍