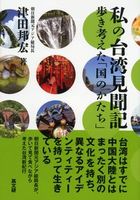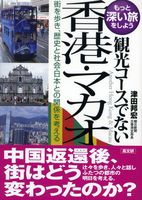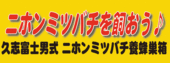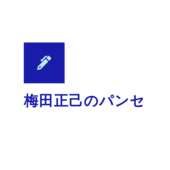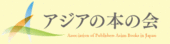- NEWS
アジア新風土記(111)アンコール・トム

|
著者紹介 津田 邦宏(つだ・くにひろ) 1946年東京生まれ。早稲田大学法学部卒業。72年、朝日新聞社入社。香港支局長、アジア総局長(バンコク)を務める。著書に『観光コースでない香港・マカオ』『私の台湾見聞記』『沖縄処分―台湾引揚者の悲哀』(以上、高文研)『香港返還』(杉山書店)などがある。 |
熱帯アジアの朽ちかけた遺跡を訪れる度、遺跡群のすばらしさとともに石像の神々らを包み込む生気に満ち溢れた自然の底知れない力を感じる。
あたかも自然と人間の英知が築き上げた遺跡との日々の「対話」を目の当たりにしているような気持になった。カンボジア北西部の小都市シェムリアップから北に10キロ、アンコール・トムの遺跡群に出会ったときもまた、何か踏み込んではならない領域に入ってしまったのではないかという畏(おそ)れにも似た思いにかられた。
1999年当時のアンコール・トム
アンコール・トムは9世紀から15世紀にかけて栄えたクメール王国の王城だった。12世紀末に即位したジャヤヴァルマン7世の時代に最盛期を迎え、タイ東北部からラオス、ベトナムの一部まで版図とした。歴代王のヒンドゥー教信仰とは異なり初めて仏教に帰依、王都としてアンコール・トムを築いた。
13世紀初めに完成した都城は広さ3キロ四方、外周12キロの環濠、高さ8メートルの城壁と5つの城門で固める。環濠の幅は約100メートルとみられ、ベトナム中部のチャンパ王国から度々攻撃を受けていたことから王都防衛を意識した城郭都市だった。アンコール・ワットの建立からは100年ほど後になる。
シェムリアップからは赤土の道が続いていた。強烈な青い空と色濃い緑の中をトゥクトゥク(三輪タクシー)で40分ほど走る。そこにアンコール・トムの南大門があった。
城郭の中は広々としていた。仏教とヒンドゥー教のそれぞれに由来する石像群が混淆として眼前に迫ってくる。回廊、壁などは何を描いたかが判然としないレリーフも少なくなく、木々の根は網の目のように絡みつき、思い思いにその「四肢」を伸ばしていた。けだるく皮膚にまとわりつくような粘っこい空気が祠堂から回廊、城壁へと漂い、日本の寺などに感じる清涼感とは程遠い雰囲気を演出していた。
クメールの微笑
王城の中心に位置するバイヨン寺院はクメール語で美しい塔という意味を持つ。
中央祠堂の四面像は穏やかな笑みをみせていた。見上げる石像の顔は大きく、石でつくられていることを忘れさせるような柔らかさをたたえていた。その深い笑みは王城の人たちが彫り上げた神々の世界にとどまらず、生きとし生きるものたちの世界にも通じるのではないかという余韻に浸らせてくれた。
「クメールの微笑み」といわれる笑みはアンコール・トムに特有なものだろうか。
チャンパのミーソン遺跡にも煌びやかな王城時代には笑みをたたえた像はあったのではないか。クメールの微笑みにも似ていたのだろうか。その思いは京都・広隆寺の弥勒菩薩半跏思惟像の微かな笑みに重なっていった。(『アジア新風土記76』参照)
バイヨン寺院の四面像は観世菩薩像のほかに、ヒンドゥー教の神々、戦士の葉飾りを被っていることからジャヤヴァルマン7世の偶像とする見方など諸説ある。寺院は様々な神を祀る寺院として存在していたという一つの証なのかもしれない。
アンコール・トムは仏教王はジャヤヴァルマン7世一代で終わり、後の王が再びヒンドゥー教を信奉したことでヒンドゥー寺院へとその趣を変えていく。
カンボジアの風土はヒンドゥー教、仏教などの神々が重層的につながり、異なる宗教の境界が緩やかというか曖昧なままに歴史が積み重ねられてきたということなのだろうか。
クメール人が9世紀末にタイ国境付近にヒンドゥー寺院として建立したプレアビヒア寺院は現在、近在の人たちが僧侶の話に耳を傾ける場になっているという。(2025年2月9日、TBSTV『世界遺産』)
厳しい自然の中でアンコール・トムの遺跡群が持ちこたえられてきたのはなぜか。最近の研究報告に答の一つをみる。
早稲田大学研究活動プレスリリース『バイヨンの謎と希望―アンコール遺跡保存協力のための日本国政府チーム30年の挑戦―』は、15メートルの砂盛土に立つバイヨン寺院が1年の半分が雨季という環境下で倒壊しなかった理由に熱帯のスコール性の降雨が大部分は基壇表面を流れ落ちることで浸透する雨量の少ないことを挙げる。ただ、地球温暖化の影響として降雨が連続的に長期にわたると推測、雨水の深部への浸透で砂盛土が弱くなることへの危惧も指摘している。(2025年1月25日)
東南アジアの人たちは温暖化を雨の降り方の変化で実感する。
雨は激しくてもかつてはほどなくすると上がったが、いまはなかなか止まず傘が必要という。この問題は一年が雨季と乾季に分かれた地域に立つ遺跡に少なからず係わってくることなのかもしれない。
アンコール・トムは1998年4月にポル・ポト派の領袖、ポル・ポトが西部の密林に死去するころまでは入ることが難しかった。どこに地雷が埋まっているかもわからなかった。
全土に長く続いた内戦の時代、ポル・ポト派は76年に民主カンプチア政権を樹立、原始共産主義を標榜して極端な農本主義をとる。都市住民の強制農村移住、知識階級の抹殺などで170万人ともいわれる人たちが虐殺された。
国連カンボジア暫定統治機構(UNTAC)の下で実施された93年の総選挙には参加せず、ジャングルに逃れてゲリラ活動を続けたが、次第に影響力を失っていった。
王城の跡を歩いたのはポル・ポトの死から1年後だった。
内戦の硝煙がまだ各地に燻っているときの邂逅は、往時を偲ぶのとはまた違った感慨を心のどこかに残した。密林を彷徨したポル・ポト派の部隊も王城に立ち入ったのだろうかということまでも想像させた。兵士たちは遺跡の一つ一つに体と小銃を預け、暫しの休息をとっていたのか。あるいは祈りを捧げていたのだろうか。
アンコール・ワットとともにカンボジア観光のスポットになったいま、再訪する機会があったとしてもそのときの心の揺れをどこまで感じられるかはわからない。
シェムリアップにはカンボジア王家の離宮があった。
シアヌーク殿下がカンボジアの象徴として輝いていたころ、殿下も時々、離宮を訪れると聞いた。日はまだ高かった。
離宮をとりまく照葉樹の高木にはオオコウモリがいた。南国の王宮に飛ぶオオコウモリを眺めながらアンコール・トムへの道を振り返った。
日が落ちて闇が深くなればなるほど、自然と遺跡群は一体化していく。すでに漆黒と化した木々と祠堂、石像は何千、何万のコウモリを道化役に、夜毎の饗宴を繰り広げているのではないか。そんなことを夢想した。
 ホーム
ホーム ご注文方法
ご注文方法 カートを見る
カートを見る お問い合わせ
お問い合わせ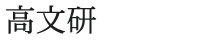
 関連書籍
関連書籍