- NEWS
アジア新風土記(23)鄧小平の香港

|
著者紹介 津田 邦宏(つだ・くにひろ) 1946年東京生まれ。早稲田大学法学部卒業。72年、朝日新聞社入社。香港支局長、アジア総局長(バンコク)を務める。著書に『観光コースでない香港・マカオ』『私の台湾見聞記』『沖縄処分―台湾引揚者の悲哀』(以上、高文研)『香港返還』(杉山書店)などがある。 |
中国の鄧小平が死去して25年が経つ。
1997年、香港返還まであと5か月という2月19日だった。北京はその夜、92歳の最高指導者が入院していた病院周辺を除いて静まり返っていた。日が変わって20日未明からメディアの動きが慌ただしくなり、香港のテレビ局は午前2時過ぎから北京の特派員が前日からの様子を伝える。朝の香港各紙はフロントページをモノクロにして哀悼の意を表した。
「鄧小平死去」を報じる中国紙(杉山正己氏撮影)
香港の人たちは返還への道筋をつけた鄧の死を来るべき時が来たと受け止める。それ以上のものではなかった。鄧は漁民が航海の守護神として信仰する「媽祖」のようなものだった。媽祖を失って、これからの航海に漠とした不安が広がる。「一国二制度」がどこまで有効かという思いにかられる人たちは少なくなかった。
香港の中国返還は82年9月24日、北京で英国のサッチャー首相と鄧小平との会談で動き出す。英国はアヘン戦争後、香港島と九龍半島を領有したものの、後背地の新界地区は99年の租借地だった。その期限が1997年に切れることから「返還問題」が現実の外交問題として浮上してきていた。交渉の一端をNHKTV「アナザーストーリーズ」の「香港返還 すべてはあの日から始まった」から拾う。
サッチャーは冒頭、新界地区の主権は返すが行政権は英国に任せてほしいと切り出す。鄧は言下に「私はあなたに同意できない」と拒否する。さらに「私は李鴻章(19世紀に英国との不平等条約によって新界地区の租借に同意した清朝の外交官)のような売国奴ではない」と言った。会談に立ち会った英外交官アンソニー・ゴールズワージーが伝える。
英国に中国が強気に出た場合の選択肢はなかった。香港植民地は新界地区を除いた香港島と九龍半島だけでは1割にも満たないうえ、市民生活に欠かせない水、野菜、肉などの大半は大陸に依存していた。自立は難しかった。
中国と英国の話し合いは鄧・サッチャー会談に先立つ3年前から実質的に始まっていたが、この時期は協議がしばしば中断された。英国の対中交渉チームの中心にいたパーシー・クラドックは『中国との格闘 あるイギリス外交官の回想』(小須田秀幸訳、筑摩書房、1997年)で「中国の指導者たちは台湾問題にかかりきりで、台湾に対して見せたほどの真剣さは香港問題ではついに見ることはできなかった」と振り返っている。
鄧は1970年代に「台湾統一」のための「一国二制度」を考えたといわれ、81年9月には葉剣英全人代常務委員長名で高度な自治を認めるなど9項目の提案を発表している。当時の最優先課題はしかし、台湾側の拒否でデッドロックに乗り上げていた。
鄧はいつの時点で「一国二制度」を香港に応用しようと思いついたのか。『中国との格闘』によれば、英国のエドワード・ヒース元首相が82年4月初めに北京を訪れたとき、鄧が彼に「台湾に対する9項目提案という線に沿って香港問題についても解決は可能だろうか」と尋ねたという。鄧・サッチャー会談の5か月前のことだ。
84年12月、中英両国は香港返還に関する共同声明に署名する。社会主義体制下の資本主義社会を50年間保障した「一国二制度」は妥協の産物だった。中国にとっては「主権の回復」であり、英国もまた「自由社会が残る」として、双方の面子は保たれた。鄧もサッチャーも一つの国家に二つの制度が併存することの整合性をどうつけるかの方程式を見出せない中での声明だった。
破綻は返還からほどなく表面化する。
香港社会の規範となる香港基本法は中国人の両親のいずれかが香港永住の権利を持つ場合、子どもが大陸生まれでも香港の市民権を得られるとしている。香港最高裁は99年1月、中国からの出国証明書を持たない大陸の子どもたち200人の永住権訴訟を基本法に則って認めるが、中国政府は出国証明書を持つ子に限るとして最高裁判決を覆す。香港の人たちは中央が香港に優先することを見せつけられた。
香港と香港人は「一国二制度」がなければ返還と同時に中国と中国人になっただろう。自由な資本主義社会はいとも容易く社会主義体制下の街になっていただろう。香港の人たちがこの制度に「自由社会の夢」を託すこともなかったかもしれない。
香港国家安全維持法施行などによって制度が瓦解したいま、「高度な自治」を求めてきた25年を誇りに、なお希望を持ち続けるのか。現実に否が応でも向き合わなければならないと改めて自覚するのか。
鄧にとって香港はどのような存在だったのか。台湾統一の望みがままならないとき、香港問題が新たなテーマとして持ち上がってきたということだろうか。屈辱の歴史に終止符を打つという気持ちはあっても、そこに暮らす人たちへの思いにどれほどのものがあったのだろうか。
中国の政治家は「青史(中国史)」に名を残すことを常に考えると香港の知人から聞いたことがある。鄧の脳裏にあったのはなにか。
「鄧小平による香港回帰」は青史に記憶されるだろう。改革開放政策はどうか。外資導入などによる経済発展を目指した政策が保守派の抵抗で進展しないなか、鄧は92年1月から2月にかけて武漢、深圳、珠海、上海などを訪れる。そのときの「南巡講話」は改革開放加速の大号令だった。深圳では国際貿易センター49階の展望レストランにも昇った。街は79年に「深圳特区」に指定され、開発が進んでいた。
92年1月、広東省を視察する鄧小平
香港は建ち始めたビルの向こうにあった。窓越しに深圳もいつか香港のような大都市になると想像したのだろうか。英国に対峙して自身がまとめ上げた返還は目前だった。「香港回帰」を実現させた指導者として香港の地に足を踏み入れるときの光景もまた、思い描いていたのではないか。
1969年、私は初めて香港に行った。
香港島からフェリーで九龍半島に渡り、中国・広東省との境界が長く続く新界地区まで足を運んだ。境界線の中程にある落馬洲地区の小高い丘に登り、深圳を見下ろした。
「香港から中国が見える場所」として知られていた丘から文化大革命の渦中にあった大陸を垣間見たいという思いもあった。
 ホーム
ホーム ご注文方法
ご注文方法 カートを見る
カートを見る お問い合わせ
お問い合わせ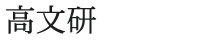
 関連書籍
関連書籍











