- NEWS
アジア新風土記(9)7月1日の香港

|
著者紹介 津田 邦宏(つだ・くにひろ) 1946年東京生まれ。早稲田大学法学部卒業。72年、朝日新聞社入社。香港支局長、アジア総局長(バンコク)を務める。著書に『観光コースでない香港・マカオ』『私の台湾見聞記』『沖縄処分―台湾引揚者の悲哀』(以上、高文研)『香港返還』(杉山書店)などがある。 |
香港の表通りから一つ、あるいは二つ脇道に入っていくと、細い道が迷路のように続いている。四季の薄い街にせめてもの彩を添える花屋があり、豆電球からパソコンメモリーまでのあらゆる家電を揃える店があり、ふと立ち止まった辻のクスノキの下には小さな廟が立っている。
高層ビルが林立するイメージとは程遠い普段着の香港がそこにあった。
大陸の人たちはいま、香港のそういった佇まいを「貧乏くさい」と表現する。
香港の人たちはかつて、大陸のテレビに映る人々の姿格好を「野暮ったい」と見下していた。
香港人が広東省との境を流れる深圳川を越えて深圳に入ると店員らは競って香港ドルを欲しがった。
その香港はいま、中国元が街に溢れ、大陸からの観光客が普通話(北京語)で声高に話しながら最新のブランド品を買う姿が日常茶飯の光景になっていた。
普通話は北京語を標準とした公用語であり「普通」は広く通用するという意味だ。
時の流れは主客転倒した香港と大陸を演出する。
2021年7月1日、返還から24年目の香港は1万人の警察官が動員される厳戒都市に変わった。
民主化・反政府デモの出発地であるビクトリア公園は封鎖され、民主派グループの行進も直ちに制止された。
香港の人たちの「声」はどこにもなかった。
7月1日、香港全警察官3万人の3分の1が街に出た
香港島・湾仔(ワンチャイ)のコンベンションセンター前での返還記念セレモニーにも小さな変化があった。
林鄭月娥(キャリー・ラム)行政長官はこの日北京で開かれた中国共産党結党100年の祝賀式典に出席、6日前に警察を統括する保安局長から昇進したばかりの李家超政務長官が林鄭長官の代理を務めた。
香港特別行政区が誕生した特別な日も、中央政府の公式行事の前には香港政府トップがいなくても問題ない「一地方都市の行事」に過ぎなくなった。
ビクトリア公園は完全に立ち入りが禁止された
中国が返還時に感じていた「香港の優位性」はすでにない。
本土の経済発展は国際都市・香港のメリットを失わせ、「一国二制度」による高度の自治と資本主義社会を享受する特権は消滅した。
北京の出先機関である中央政府駐香港連絡弁公室(中弁連)には香港の日常語である広東語(香港語)を話す職員がいないといわれる。
香港を理解する必要はないとも取れる姿勢が現状を端的に物語る。
中国はさらに本土のようなハイテクを駆使した管理社会の徹底を目論む。
ネットメディアの取り締まり強化も始まっている。
若者らの情報交換手段だったSNSはすでに監視されている。
新聞、地下鉄広告などの繁体字は簡体字に直さなくてはという声も強くなっていく。
中国教育部が香港での普通話、簡体字の普及を加速すべきだという報告書をまとめたとも伝えられる。
香港の人たちは返還後も香港政府に対抗してきた。
2003年、香港基本法23条にある国家分裂・反乱扇動などを禁止する法の制定に反対する50万人デモが起き、12年には愛国を強調する教育方針を撤回させた。
しかし、行政長官直接選挙を求めた14年の雨傘運動は金融街を一時占拠したものの警察当局の強制排除と過剰警備を正当化させた。
19年の逃亡犯条例改正案反対運動でも北京の「圧力」に屈せざるを得なかった。20年の香港国家安全維持法(国安法)は「一国二制度」を完全に崩壊させた。
本土化にどこまで抗うことができるのか。
普通話しか話せないオーナーのレストランを使わず、大陸商品を扱う店にも立ち寄らず、家庭では普通話のテレビ番組を見ないといったささやかな抵抗は続いている。
政府の密告奨励、警察の潜入捜査への対抗策として、信頼できる友人だけの小グループで行動するようにもなった。
平和的手段による改革に絶望する若者らは警察部隊との激しい衝突も躊躇しなくなった。
大陸に関心はなく、香港が「本土」だとする「本土派」と呼ばれる人たちも生まれた。これまでの「香港社会」を維持していく力になるかは定かではない。
21年の7月1日は夜にも動きがあった。午後10時ごろ香港島の繁華街で警察官が50歳の男に刃物で刺され重傷を負った。男は自殺を図って病院で死亡する。
6日には中高校生6人を含む15歳から39歳の男女9人がテロ容疑で逮捕された。
香港独立を目指す組織「光城者」のメンバーといわれ、海底トンネル、鉄道、裁判所などの公共施設の爆破を計画していたという。
拠点とした九龍半島のホテルの一室からは15年のパリ同時多発テロに使われたとされる高性能爆薬「過酸化アセトン(TATP)」が見つかった。
2つの事件が「暴徒」「自暴自棄の若者」による一過性のものではなく、直接的な暴力に訴える動きが拡散していくのではという恐れは捨てきれない。
香港人が求める自由な社会とはなにか。
その答えの一つに「光復香港」というキャッチフレーズがある。
「光を取り戻す」という意味は、かつての植民地時代の自由放任主義のような社会しか思い描くことができないということか。
保守回帰ともいえるアピールは、「独立」という未来が夢のまた夢であるという諦観、自覚から生まれてくるものなのか。
1日朝、ビクトリア港・スターフェリーの新聞売り場に、香港島を走るトラムの新聞スタンドに蘋果日報(アップル・デイリー)はなかった。
同紙は6月24日、発行を停止した。本紙20ページ、別刷り12ページの最終号は、通常の10倍を超える100万部が印刷された。
物心両面で支えていた創業者の黎智英(ジミー・ライ)氏は外国勢力と結託などの国安法違反容疑で逮捕・収監され、編集幹部も同法違反で相次いで逮捕された。
銀行口座は凍結され、金融機関などからの支援策も封じ込められ、万策尽きての「廃刊」だった。
蘋果日報最終号。1面に「香港人、雨中の辛く悲しい別れ」「頻果を支持する」とあった
蘋果日報は1995年に創刊され、大衆紙の色合いを強く滲ませる新聞だった。
ジャンルを問わず自由な論調を展開する一方でセレブのゴシップ、交通事故のどきつい写真を1面に堂々と載せた。
中国資本の入った有力紙が次々に中央・香港政府寄りにシフトしていく中、いつの間にか自由を求める香港のフロントランナーになっていた。
1部10香港ドル(約140円)は他紙より割高だが、良くも悪くも街の姿を映し出す紙面に人々は飛びついた。
香港と広州を結ぶ九広鉄道の香港側の最後の駅に羅湖(ローウー)がある。
ホームにはいつも大量の蘋果日報が捨てられていた。
本土で官憲から咎められるのを恐れる人たちが処分するからだ。
羅湖に「新聞」はもう一つも落ちていないだろう。
 ホーム
ホーム ご注文方法
ご注文方法 カートを見る
カートを見る お問い合わせ
お問い合わせ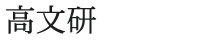
 関連書籍
関連書籍











