- NEWS
アジア新風土記(8)沖縄・慰霊の日

|
著者紹介 津田 邦宏(つだ・くにひろ) 1946年東京生まれ。早稲田大学法学部卒業。72年、朝日新聞社入社。香港支局長、アジア総局長(バンコク)を務める。著書に『観光コースでない香港・マカオ』『私の台湾見聞記』『沖縄処分―台湾引揚者の悲哀』(以上、高文研)『香港返還』(杉山書店)などがある。 |
沖縄に「若夏」という言葉がある。「うりずん」が終わったあと、旧暦4月から5月にかけての季節のことだ。冬の北東季節風の合間をぬう柔らかな南風に包まれるうりずんに芽生えた草木は、やがて若夏になって野山が緑色濃く染まっていき、枝の先々、葉の先々に活力を蓄えていく。大地が1年で最も生命力に満ちるとき、沖縄は鎮魂の祈りを捧げるときを迎える。
沖縄の戦争は、沖縄の風土が自然も人もみな命が躍動する最中の戦いだった。住民を巻き込んでの地上戦は、1945(昭和20)年4月1日、連合軍による沖縄本島の読谷・渡具知海岸への上陸に始まり、沖縄防衛にあたっていた第10方面軍第32軍司令官牛島満中将の6月23日の自決をもって終結とされた。中将の自決は22日という説もある。
沖縄はこの日、生き残った人たちが20万人を超える戦没者の霊を追悼する。2021年6月23日もまた、人々はコロナ禍と大雨の中でも、摩文仁の丘に、各地の慰霊碑、ガマに足を運んだ。
米軍統治下の琉球政府は1961年、牛島中将の自決を22日として「慰霊の日」を定めたが、65年に再調査を踏まえて23日に変更する。日本復帰後は74年の「慰霊の日を定める条例」で、改めて県民の平和を祈る日になる。91年の地方自治法改正によって地方公共団体が独自に休日を定めることが可能になり、役所、病院、学校もすべて公休日になった。
沖縄独自の慰霊の日に、台湾の「2・28事件」の休日を思い起こす。
戦後の47年2月27日夕、台北旧市街でヤミたばこを売っていた女性が大陸出身の官吏らに商品と現金を奪われたことをきっかけにして、28日から国民政府・軍への抗議行動が台湾全島に広がった。台湾省政府は台湾人への無差別弾圧・殺戮を繰り広げ、死者・不明者は推定で最大2万8000人ともいわれる。全容はまだ明らかになっていない。
台湾政府はこの事件を忘れてはならない記憶として、2月28日を「和平記念日」の休日とする。その思いは、沖縄の慰霊の日に通じる。
休日にしてどれほどの意味があるのか、という意見は台湾にもある。
しかし、「2月28日」を休日とすることで、人々は心落ち着かせて過去と向き合うときを得る。沖縄の「6月23日」もまた、そのような意味、意義を持っているのではないか。
日本の社会は、第2次大戦の敗戦の日を、広島と長崎の原爆投下日を、亡き人々を追慕する日として共有する。追悼行事が全国紙の1面、テレビの全国ニュースのトップになることを当たり前のこととして受け止める。しかし、沖縄の慰霊の日はどうだろうかと思う。戦争への感覚的な相違がそこにあるのではないか。
その差とはなにか。本土では地上戦を経験しなかったことによるのか、あるいは沖縄という琉球処分で獲得した「外地」の戦争だったからか。
大戦末期の軍部の動きは、本土と植民地台湾を重視する。
44(昭和19)年7月、西太平洋サイパン島が陥落する。連合軍の優勢はすでに揺るがなくなっていた。大本営は連合軍の次の攻撃目標が台湾か沖縄かの判断に迷う中、9月に台湾、沖縄をカバーする第10方面軍を新設する。司令官は台湾総督を兼務する安藤利吉だった。
台湾上陸を想定しての作戦は、11月には沖縄に配備されていた最精鋭部隊、第9師団の台湾転進を決定する。同師団の後を埋めるはずだった姫路の第84師団は、本土防衛を最優先する方針によって派遣が見送られた。
沖縄より台湾に重きを置いた作戦は軍事的な理由だけだったのか。
1895(明治28)年、日清戦争後の講和条約で清朝に台湾割譲を認めさせた日本は、沖縄に比べてより重要かつ価値ある存在という認識に基づく植民地経営を敗戦まで続ける。1934(昭和9)年に台湾を視察した井野次郎・沖縄県知事は「台湾の事業は何れを見てもその大規模なるに一驚を喫した、(中略)我々の眼からすると却つて贅沢すぎると思はれる位大規模な設備がしてある、すべては金の力によつて台湾の開発が出来たわけだと感じた」と述べる。(1934年4月18日付け「琉球新報」)
戦力の空白地帯になってしまった沖縄は、連合軍の上陸作戦を容易にした。その様相を『観光コースでない沖縄(第3版)』(高文研、1997年)にみる。
日本軍はサイパン陥落後、南西諸島に航空基地を置く必要に迫られ、読谷と嘉手納(北谷村)の飛行場を突貫工事で完成させる。第32軍はしかし、兵力補充が見込めないために両飛行場を放棄、首里の軍司令部一帯に集結した。読谷・渡具知海岸に上陸した米軍は、ほとんど反撃を受けずに北(読谷)と中(嘉手納)の飛行場を手に入れる。
地上戦は牛島中将の自決によって終わったわけではない。戦線は首里から南部へと拡大していき、将兵の「玉砕」、住民の「集団自決」が続いた。本土決戦を覚悟する大本営はその態勢を整えるまでの「時間」を沖縄に課した。軍部は沖縄を本土の一部とは見なさず南方戦線の延長線上に位置すると考えていたという指摘もある。
本土防衛の「捨て石」としての地上戦は「沖縄軽視」そのものだった。そのことが沖縄の戦争を本土の戦争とは別の次元のものにしてしまったのではないか。
本島中南部の山野には、朽ちるにまかせた遺骨がいまもさらされている。
2021年5月14日、玉城デニー沖縄県知事は、防衛省の米軍普天間飛行場移設先の辺野古埋め立てに本島南部の土砂をあてる計画に関して、関係機関、業者らの遺骨有無の確認を求めた。地中になお幾多の遺骨が眠るとされ、遺骨の混じる土砂が使われるのではという反発が起きているからだ。遺骨を拾い続ける市民団体代表のハンガーストライキもあった。
日本人の「遺骨」に対する強い思い入れは、戦没者の遺骨収集事業が継続され、東日本大震災の不明者を捜す取り組みでもわかる。本土のどこかで沖縄と同じようなことが想像できるかと自問するとき、「外地」の戦争への思いは膨らんでいく。
若夏の季節が終わるころ、梅雨明けと夏の到来を告げる「カーチーベー(夏至南風)」が吹き始める。1945年夏のカーチーベーは、どんな風だったのだろう。
 ホーム
ホーム ご注文方法
ご注文方法 カートを見る
カートを見る お問い合わせ
お問い合わせ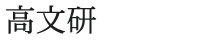
 関連書籍
関連書籍











