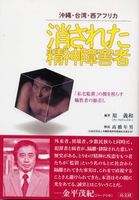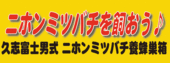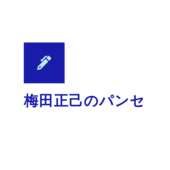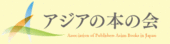- NEWS
「消された精神障害者」和解のご報告 2025年7月25日
① 和解の成立について
映画「夜明け前のうたー消された沖縄の障害者」の公開後、映画の原作書籍である「消された精神障害者」に登場する私宅監置された被害者のうち、ひと組の家族から、作品内容について苦情が申し立てられていましたが、同家族から、去年(2024年)2月、民事訴訟が提起されました。
訴えられたのは、監督である私(原義和)と映画製作に関わった他3名で、映画と書籍の一部内容が名誉を棄損しているとの訴えでした。私たち被告側は名誉毀損には当たらないと考え、争うことにしました。その後、裁判所の判断として、和解をするのが望ましいとの強い勧めがあり、原告側がそれを受け入れたことを受け、私たち被告側としても和解に応じる判断をしました。去る2025年6月12日、和解が成立しました。
和解にあたり、以下(1)から(3)の事実を確認し公開することとなりましたので、まずそれを列記し、その後に補足の説明を付記致します。
(1) 被告らは本件書籍の製作に際し、原告らという亡金太郎の子らが存在することを知っていたものの、被告原の島民に対する取材において、原告らの連絡先を尋ねたが、これを拒まれたことを踏まえた総合的な検討の結果として、原告らに対する取材を実施しないという判断をしたこと。
(2) 本件書籍に登場する取材対象者は、被告原による取材を受けた際に、初めて亡金太郎の長男の侑の存在を知ったものであり、同氏が本件書籍において亡金太郎ないし原告らについて語っている部分の描写は、同氏が被告原による取材を受ける中で認識した事実関係に基づく主観であること。
(3)本件書籍上で描写されている「大家族のような島人たち。その輪に入れない人がいる」「私宅監置の制度によって、島から排除された人である」「家族もまた”島に戻りづらい”“戻れない”という形で、島人たちの輪からはじかれていた」という部分について、亡侑が1995年のミャークヅツに初出現(ウイディウヤ)として帰島し、原告成吾が2003年に同様に帰島するなど、現に原告らにおいて当該島に帰島する機会があったこと。
② 以下、和解の公開文書の補足説明です。
書籍「消された精神障害者」は、1960年代に沖縄各地で行われていた精神障害者に対する私宅監置の実態を明らかにしようと試みた作品です。ある医師が当時撮影した現場の写真をもとに、その関係者を訪ねて聞き取りをし、残された資料を集めるなどをして執筆したルポルタージュです。
私宅監置は、精神障害者を狭い小屋や家の裏座などに長い期間閉じ込め、人生の自由を奪ってしまう措置でした。家族が勝手におこなった私的措置ではなく、法律に基づく制度措置であり、保健所や警察が介入して行われた社会的隔離でした。しかし私宅監置の事実は、それが終わった後も触れてはならない“禁忌(タブー)”のように徹底的に伏せられ、表で語られることはありませんでした。ですから、書籍にも記しているように、関係者に取材を試みた際、怒鳴られるなど露骨に嫌悪感が示されたこともあり、取材は薄氷を踏むような難しい行程の連続でした。
(1) について
原告の父親である金太郎さんも、私宅監置の現場写真をもとに取材をした被害者のひとりです。私は他の被害者の取材と同様に、金太郎さんが隔離されていた島に足を運び、聞き込み取材をしました。
その際、長男の侑さんが大阪で暮らしていることを聞き、連絡を取ろうとしたのですが、既に亡くなっていたことが分かりました。侑さんに妹弟(原告)がいることも分かり、それを教えてくれた人に連絡先を尋ねましたが、強く拒否され、その後も繰り返し連絡先を尋ねましたが、その人の拒む意思は頑なでした。私はそれ以上踏み込むことは島の人びとに悪影響をもたらす危険があると判断し、妹弟への取材を断念しました。そうしなければ何らかの揉め事を引き起こしていた可能性があり、取材時の現場判断として間違っていたとは考えていません。金太郎さんが晩年に入院した病院の元看護師への聞き取りや、金太郎さんについて記した古い論文の入手など、周辺取材は比較的しっかり出来たことから、金太郎さんの社会的隔離の骨格は把握できたと判断しました。
(2) について
書籍では、長男の侑さんをはじめ金太郎さんの子どもたちについて、ある方がインタビューに答えています。「本件書籍に登場する取材対象者」とは、その方のことを指しています。その方と監督の私は、金太郎さんやその一家が見舞われた諸状況について、別の島の人から一緒に話を聴くなどして把握に努めました。収集した情報を踏まえ、侑さんの苦悩の人生に思いをめぐらせて語られたのが、その方のインタビュー証言です。私宅監置の後、一家が生活基盤を揺るがされていたことなど、一定の事実を把握した上で語られた主観であり、金太郎さんや侑さんに対する、同じ島民としての共感や愛情に満ちた語りでした。私は、被害者の痛みへの共感こそが、私宅監置のような人権蹂躙制度を終わらせ、新しい扉を開く希望になると信じており、このインタビュー証言を書籍で用いました。
金太郎さんの家族である原告が、こうしたインタビュー証言とは異なる主観を持つのは当然かもしれません。しかし一般的に、私宅監置を受け入れざるを得なかった家族は、檻の内側と外側で引き裂かれるような過酷な立場に置かれたため、主観に一定のバイアスがかかるのも事実です。取材者としてこうした点も考慮して書籍全体を構成しました。
(3) について
侑さんが島を離れてから亡くなるまでには、約半世紀の月日があります。その間に何度か帰島する機会があったことを書籍が否定するものではありません。帰島の回数など、その詳細を把握することは困難であったため、書籍では「島に戻りづらい気持ちになったのは想像に難くない」と推察に依っていることを明らかにしています。書籍が焦点にしたのは帰島の有無ではなく、侑さんの胸中の苦悩であり、いかにつらく悲しい思いを抱えて生きねばならなかったかという、いわば魂の被害についてです。私宅監置はまぎれもなく、ひとりの障害者を島社会から排除してしまう制度だったのであり、聞き取りによって得た証言では、家族にも大きな被害が及んでいたことが示されています。ある島民の眼には金太郎さんの子どもが「(島を)逃げた」ように映っていたことや、その後、一家が島に住むための生活基盤を揺るがされていたことなど、私宅監置が、金太郎さんひとりを社会的に排除しただけに留まらない残酷な制度であったことを知らされたのです。それが「家族もまた”島に戻りづらい” “戻れない”という形で、島人たちの輪からはじかれていた」という表現の本質です。
侑さんは父親が私宅監置されたことで故郷の島との間に一定の心理的距離ができてしまったのではないか、それは社会的に検証されるべき家族としての制度被害ではないかということを問うているのです。侑さんが深い苦悩を内に秘めてその後を生きたであろうことを思い描き、そうした社会制度を許してしまった市民のひとりとして、私はその実態を世に示し、共にその罪責を担う決意を示したいと考えたのです。
③ 最後に、和解を被告として受け入れた理由について記します。
原告である金太郎さんの家族は、私宅監置制度の被害者だと、私は考えています。
もちろん第一の被害者は隔離された当事者である金太郎さんです。それを抜きにこの問題を語ることはできません。しかし、侑さんをはじめ家族も、別の形で被害を受けたに違いないのです。その被害は手当てされることも、社会的に検証されることもありませんでした。当事者や家族は、半世紀もの長い月日を、とてつもない傷を引きずりながら生き延びねばならなかったはずです。
今、そのトラウマは心の奥深くに沈殿し、蓋をされ、当人らにとってはまるで傷が治ったかのように感じられるかもしれません。しかし、果たして本当にそうなのか。社会的に共に担うべき痛みが心の奥底にあり続けているのではないか。トラウマをもたらした社会の罪責を不問に付してよいのか。書籍はそれらを問うています。
当事者や関係者のトラウマからの解放は、私宅監置制度の検証や総括といったプロセスの中で徐々に果たされていくものだと考えます。今回のこの和解プロセスもその一助になることを切に願うばかりです。
被害者でもある家族と私たちとは、本来、協働関係にあるのが望ましく、訴訟によって対立関係になることは望んでいませんでした。しかし、名誉毀損などの訴えは到底受け入れることができないため、争わざるを得ませんでした。
今回、原告が裁判所の提示する和解案を受け入れたのは、名誉毀損の成立を断念したと受け取れるものでした。その和解案をはねつけてまで、こちらが徹底的に判決で結着をつけようとすると、対立関係をより深めてしまいます。それは私たちの意に反することであり、和解を成立させることが望ましいと判断しました。上記の通り、映画の背景となる事実の確認を合意することによって、金銭によらない平和的な結論を導き出すことができたと受けとめています。
原告被告それぞれに異なる思いがあったとしても、裁判所の努力によって、言葉を厳選しながら双方が納得する事実が明文化され、和解という社会的結着がなされたことは一つの画期として尊重されるべきです。
あらぬ誤解を避けるため、上記(1)から(3)を書籍は微塵も否定しておらず、和解によって映画の間違いが確認されたわけでも、修正が勧められたわけでもないことを確認しておきます。
今後も書籍「消された精神障害者」の販売は継続して参ります。
現代の生きづらさを考える上で、私宅監置の闇の歴史を見つめ続けることはますます重要になっています。書籍が投げかける問いは決して色褪せていないのです。隔離された当事者たちは見殺しにされ、痛みを抱えたまま、この世を去ってしまいました。隠されてきた人権蹂躙の実態を明らかにし、彼らの損なわれた尊厳を回復し、障害者を見殺しにしない真の共生社会を創造するべく、今後も精進したいと思います。
2025.07.25
書籍「消された精神障害者」
著者 原 義和
 ホーム
ホーム ご注文方法
ご注文方法 カートを見る
カートを見る お問い合わせ
お問い合わせ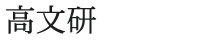
 関連書籍
関連書籍